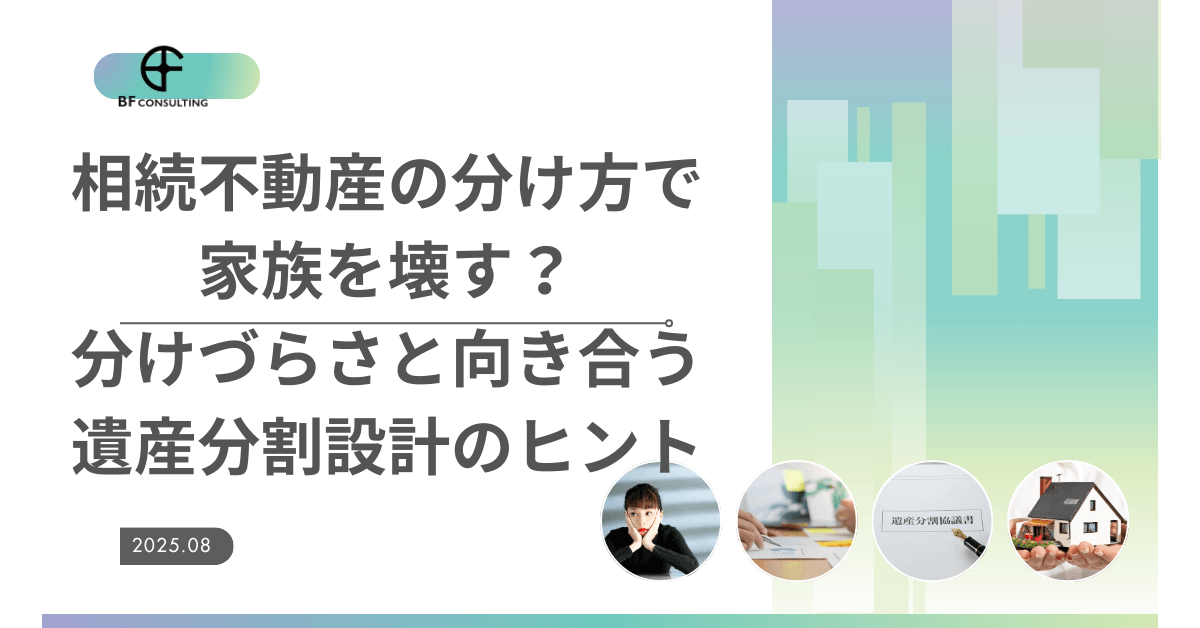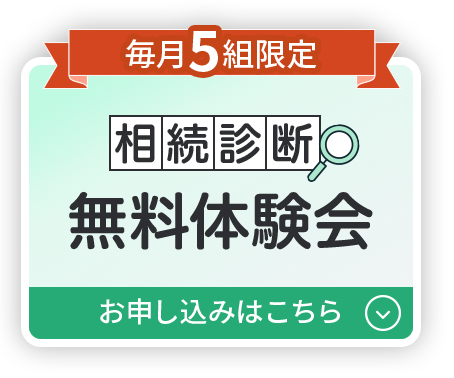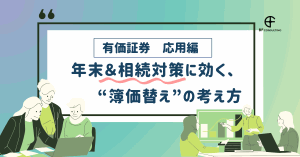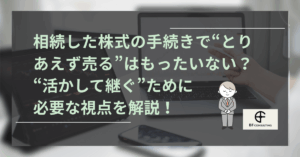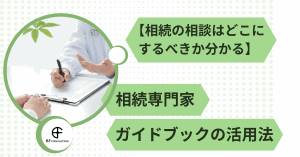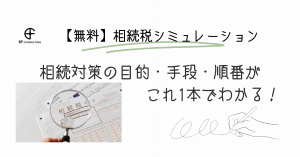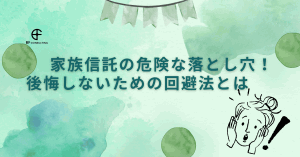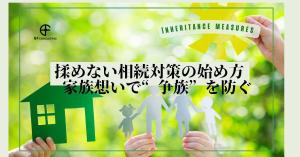「実家の土地や建物をどう分ければいいのか分からない」「不動産の相続って評価額も分け方も複雑で、トラブルになりやすいって本当?」
そう思う方もいるのではないでしょうか。
不動産は現金のように簡単に分けられず、評価額の基準も複数あるため、“納得できる分け方”を見つけるにはポイントを押さえた準備と家族間の合意形成が欠かせません。
今記事では、不動産が分けにくい理由、換価分割・代償分割・共有などの分け方3パターン、土地の相続手続きの流れ、相続後の活用・売却・国庫帰属といった取り扱い方法まで、具体例と注意点を交えて解説していきます。
遺産分割のトラブルの火種は「不動産」
「実家の土地と建物をどう分けるか」で揉めてしまい、兄弟姉妹が絶縁状態になる。
これは、決して珍しい話ではありません。
実は、相続トラブルの多くは“遺産の額”ではなく、“不動産の分けにくさ”から始まります。
「うちは自宅と少しの現金しかないから、そんなに財産はないからもめないよ」
ご相談者様からよく聞くお話ですが、相続財産に不動産が多くを占めているご家庭ほど、早めの準備が欠かせません。
5,000人を対象にしたアンケートでは、356人が相続経験者でトラブルを経験したと回答しました。更に相続トラブルを経験した356人を対象に、経験したことがある相続トラブルの内容を、10個の選択肢から回答していただきました。
最も多かった回答は「遺産分割に関するトラブル」であり、356人中198人となる55.6%が遺産の分け方についてトラブルに発生したことがわかりました。

調査会社:株式会社アシロ
調査対象: 20代以上の男女5,000人を対象とした遺産相続に関するアンケート調査
(20代458名、30代888名、40代1,330名、50代1,313名、60代以上1,011名)
調査方法: Freeasyを用いたインターネットリサーチ
調査日 : 2023年11月24日(金)~2023年11月28日(火)
なぜ不動産は“分けづらい”のか?3つの理由
不動産には、預貯金や株式とは違う3つの理由があります。
- 物理的に分けられない
- 評価額が不明確(実勢価格と固定資産税評価額が違う)
- 維持・管理・税金など、引き継いだ後の負担が大きい
特に一つしかない「実家」や「賃貸物件」を、どう誰に引き継ぐかは、感情の問題にも直結します。
物理的に分割できない
現物資産である土地や建物は、法定相続分で機械的に切ることが難しく、分筆登記や建物の取り壊しが必要になる場合もあります。
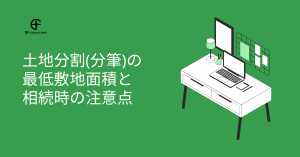
評価額が不明確
預貯金と違い、不動産には複数の評価額(実勢価格、路線価、固定資産税評価額、公示価格)が存在します。これを理解せずに遺産分割協議を進めると、「不公平」「不透明」という不満が生まれます。
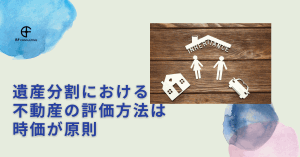
維持管理・税金の負担
相続後には固定資産税や修繕費、管理費、さらには賃貸経営の場合は税務申告や入居者対応も必要です。事前に負担やリスクを把握しないと、負動産化する危険があります。

不動産の価値はひとつじゃない!?「一物四価」に注意
不動産を相続するとき、「この土地は〇〇万円の価値があるから、こう分けよう」という話し合いが前提からズレていることがあります。
なぜなら、不動産には「価値が一つではない」という特徴があるからです。主な4つの評価基準(実勢価格・固定資産税評価額・路線価・公示価格)はそれぞれ目的が異なり、金額もばらばらです。
| 評価の種類 | 主な使い道 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 実勢価格 | 売買時(市場での価格) | 最も高くなることが多い。エリアやタイミングで大きく変動する。 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税や都市計画税の計算に使用 | 実勢価格の約70%程度が多い(自治体により差あり) |
| 路線価 | 相続税・贈与税の計算に使用(国税庁が公表) | 実勢価格の80%程度を目安に設定されるが、必ずしも一致しない |
| 公示価格 | 不動産取引の参考、国土交通省が公表 | 市場価格の指標だが、年1回しか更新されないためラグがある |
たとえば、同じ土地でも「売れば5,000万円だけど、相続税の評価上は3,800万円、固定資産税評価は3,000万円」というように、目的によって価格が違うのです。
この違いを知らずに遺産分割を進めると、不公平感や誤解が生まれ、相続人間のトラブルの原因になります。
評価の前提を揃えることが、公平な相続の第一歩です。一物四価については、下記の記事で詳しく解説しています。
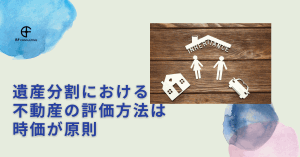
よくある失敗事例とその背景
たとえば、長男が実家を引き継ぎたいと思っていたが、他の兄弟が現金換算した「取り分」を主張して対立したケース。よくある失敗事例について見ていきましょう。
状況1:長男が実家を取得、他兄弟が不満
「兄が土地をもらって5,000万円分取ったのに、弟の私は現金で2,000万円だけ(怒)」
兄は「評価額(路線価)通りだから平等」と思っていても、他の兄弟は「市場価格ベースで不公平」と感じる。
状況2:共有で相続し意思決定ができない
「兄弟で共有」にしたものの、売却や建て替えで意見が合わず何年も放置されてしまうなど、意思決定ができずに家族関係が悪化した例もあります。
状況3:賃貸物件を相続したが“負動産”化
不動産の管理の面から「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまうケースもあります。
「アパートを引き継ぐから固定資産税くらい払えばいいと思ったら、修繕費の負担や税申告の手間が想定より重かった」
財産だけでなく賃貸経営も相続する、この部分の引継ぎを疎かにするとせっかく稼ぐ資産として遺した不動産も「負動産」になってしまいかねません。
不動産の分け方(分割方法)3パターン
不動産の分け方(分割方法)は、換価分割、代償分割、相続人全員で共有の3つの方法があります。
「不動産はあるけれど現金が少ない」場合は特に、分割方法に工夫が必要です。
究極、不動産を“平等”に分けるとしたら以下のいずれかの方法に集約されます。
- 売却して現金化(換価分割)
- 誰かが引き継ぎ、他の相続人に代償金を払う(代償分割)
- 共有にする
それぞれにメリット・デメリットがありますが、特に“共有”は将来のリスクが非常に高いため慎重に検討すべきです。
①換価分割
不動産を売却し、その代金を相続人間で分ける方法。最も公平とされ、実務的に多く利用されています。
メリット
- 現金で分割できるため、相続人間でのトラブルや不公平感が少ない。
- 売却後は固定資産税や管理費などの負担がなくなり、納税も現金で行えるためスムーズ。
デメリット
- 売却に反対する相続人がいると進まない。
- 買い手がいなかったり、売れても思った価格で売れない場合もある。
- 譲渡所得税や仲介手数料、リフォーム費用など、売却にかかる費用が利益を圧迫することも。
②代償分割
不動産をある相続人が取得し、その代わりに他の相続人に現金などで代償(清算)する分割方法です。
メリット
- 相続人の一人がそのまま住み続ける(例えば実家)ことができ、資産価値も維持しやすい。
- 被相続人と同居していた相続人が取得すれば、小規模宅地等の特例による相続税の大幅な軽減が受けられる場合もある。
デメリット
- 代償金の算定や支払いが難しく、話し合いがまとまりにくい。評価基準(実勢価格・路線価・固定資産税評価額など)が焦点となる。
- 支払い能力のある相続人でないと成立しづらく、場合によっては分割払いや担保が必要になることも。
③共有分割
法定相続分に応じた共有として遺産分割協議を締結する形態です。
将来の売却や変更に全員の同意が必要となることで意思決定が困難になる恐れもあります。
現物分割もありますが...
分筆登記により、権利がシンプルになるメリットもありますが、土地の形状や面積が変わり、不動産価値が下がる恐れあり。特に投資用としての活用が難しくなることも。
さらに、分けても道路への接道状況などに偏りがあり、不公平感が残るケースもあります。
分筆については、下記の記事にて詳しく解説されています。
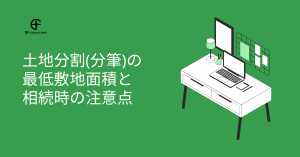
どの分け方にも一長一短があり、相続人全員の合意、評価額の透明性、資金負担能力が重要な判断軸になります。状況に応じて、専門家(司法書士・税理士・弁護士)への相談も視野に入れて検討しましょう。
土地の遺産相続手続きの流れ
土地を含む相続では、手続きの抜けや遺産分割の漏れがトラブルにつながりやすいものです。
以下の流れに沿って準備すれば、手続きの遅れや相続人間の不公平感を防ぎつつ、スムーズに進められます。
相続人を確定する
チェックポイント:被相続人(故人)の戸籍謄本を取得し、法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)を正確に確定することが第一歩です。
この記事では、手続き開始には必須とされています。
事前対策:相続人の漏れを防ぐため、専門家(司法書士・弁護士)による相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成も有効です。
遺言書の有無に応じて遺産を分割する
チェックポイント:
- 遺言書がある場合は、その内容に従い「遺言による相続登記」が基本です(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要)。
- 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が・何を・どれだけ取得するか」を協議書として文書化することが求められます。
事前対策:
- 誤解やトラブルを避けるために、評価額(実勢価格/路線価/固定資産税評価額など)を相続人間で共有。
- 遺産分割協議書には、取得割合や代償分割の有無、共有状態にするか等を明記しておくと安心です。
相続登記(名義変更手続き)をする
チェックポイント:
- 遺産分割の結果に基づき、法務局へ相続登記を申請。
- 令和6年4月1日以降、相続登記が義務化され、相続発生から 3年以内に手続きを済ませなければ罰則(過料)が生じます。
事前対策:
- 必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明など)を早めに集めて整理。
- 手続きミスや手間を避けるため、司法書士への依頼も検討しましょう。
相続税を申告・納付する
チェックポイント:
- 相続税の申告・納付は、相続開始から10か月以内が期限です。必要な相続税評価額(基礎控除後の課税遺産総額)を正確に算出する必要があります。
事前対策:
- 路線価や固定資産税評価額をもとに、土地の評価書を専門家(税理士)に作成依頼するのがおすすめです。
- 基礎控除の計算(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)や控除適用項目の確認も忘れずに。
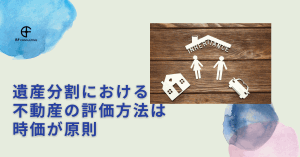
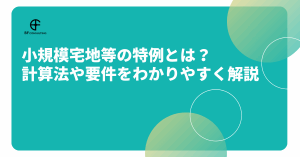
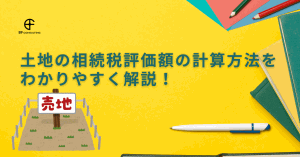
相続した土地はどのように取り扱うか?
土地を相続した後、その扱いには主として 活用する、売却する、国に帰属させる という3つの選択肢があります。
それぞれのメリット・デメリット、注意すべきポイントを踏まえて整理しました。
活用する
相続した土地を活用して資産価値を維持・向上させる方法です。
| メリット | ・賃貸(住宅用・駐車場)や農地活用、資材置き場など、収益源として活用することで、固定資産税や管理費の負担を相殺できる。 ・家族信託や共有持分の整理を通じて、円滑な遺産分割と未来世代への引き継ぎにもつながる。 |
|---|---|
| デメリット・注意点 | ・管理に時間・コストがかかる(草刈り・建物の維持など)。 ・共有状態の場合、意思決定が難しくなりがちで、将来的にトラブルの火種になる可能性がある。 |
| ポイント | 活用を検討する際は、地域の需要(駐車場としての利用可否など)や収益性を専門家に相談し、利用可否とリスクの把握を行いましょう。 |
まずはどういったことにコストがかかるか把握しませんか?下記の記事ではランニングコストを一覧表で表し、わかりやすく解説しています。

土地活用の方法は様々ですが、大切なのは自分の軸を持ち、なぜこの活用方法にしたか?明確にすることです。
そのためには、最低限の知識を身につける必要がありますが、そういった土地活用や不動産投資に関する網羅的な知識を身につけられるものに、不動産実務検定があります。
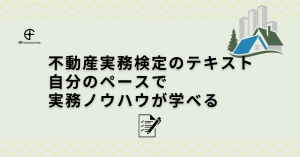
売却する
土地を市場で売却して現金化し、換価分割によって公平に相続人間で分配する方法です。
| メリット | ・現金化によって分けやすく、「誰がどれくらい取得するか」の明確化が可能。 ・固定資産税や管理負担から解放され、相続の清算がスムーズ。 |
|---|---|
| デメリット・注意点 | ・土地の評価額(実勢価格、固定資産税評価額など)に基づいた価格で売却できないことも。 買い手がつかない場合や、思った価格で売れないケースも多く、売却費用(仲介手数料、譲渡所得課税)も発生。 ・売却を巡って相続人間で意見の対立が起こることも。 |
| ポイント | 不動産会社や税理士などの専門家への依頼で、適正価格の見積もりや売却タイミング、節税対策などを相談しましょう。 |

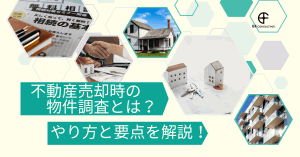
国庫に帰属させる
使い道がなく、管理負担ばかりの土地については、「相続土地国庫帰属制度」によって、国に所有権を移転する選択肢があります。
令和5年4月27日施行の新制度で、相続または遺贈によって取得された土地を、法務局を通じて国に帰属させることができます国が引き継ぐ土地は、 所有者不明土地や管理困難な土地(山林・農地など) が対象となり、固定資産税の負担や維持管理の手間から解放されます。
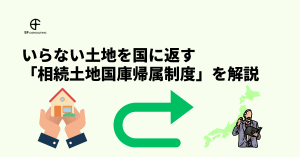
| メリット | ・不要な土地だけを手放すことができ、他の遺産(預貯金や現物財産)はそのまま相続可能。 ・管理や税負担、事故リスクなどから解放される点が大きなメリットです。 |
|---|---|
| デメリット・注意点 | ・審査が厳しい:建物・境界不明・傾斜地・権利関係ありなどの土地は対象外に。 ・承認後に10年分の管理負担金を納付する必要あり。 ・手続きには時間(半年〜1年)や専門的な知識が要求され、相続人全員の同意が必要となる場合も。 |
| ポイント | まず土地の状態(境界、建物有無、傾斜、権利関係)を測量士や司法書士に確認。必要なら境界確定や工作物撤去などの事前整備を行い、制度の承認確率を高めることが重要です。 |
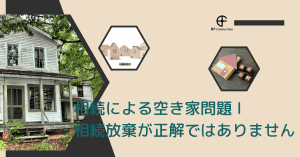
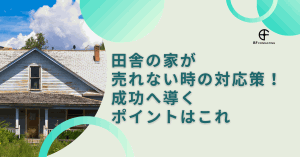
判断のカギは「現状の把握」と「家族の対話」
冷静な判断にはまず現状の整理が欠かせません。
- その不動産は誰にとって必要か?
- 固定資産税や管理費、修繕の予定は?
- 市場価格や貸し出し可能性は?
- 相続人それぞれの希望や生活状況は?
こうした情報を「ヒト・モノ・カネ」の視点で見える化し、家族で対話することが大切です。
分けにくいからこそ、対策は“今”
不動産は分けにくい財産であるがゆえに、“完全な平等”な分け方は現実的に困難です。
評価方法もひとつではなく、感情的な価値も含まれます。だからこそ大切なのは「納得感」と「思いやり」。
“等しく”ではなく“それぞれが納得できる”分け方を目指すためには、元気なうちに家族で率直な話し合いを始めることが、何よりの相続対策となります。