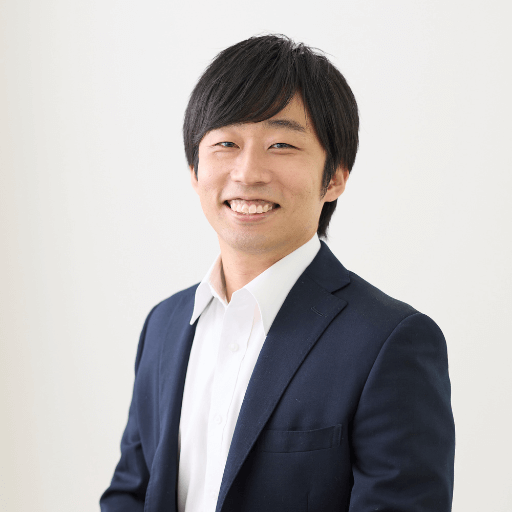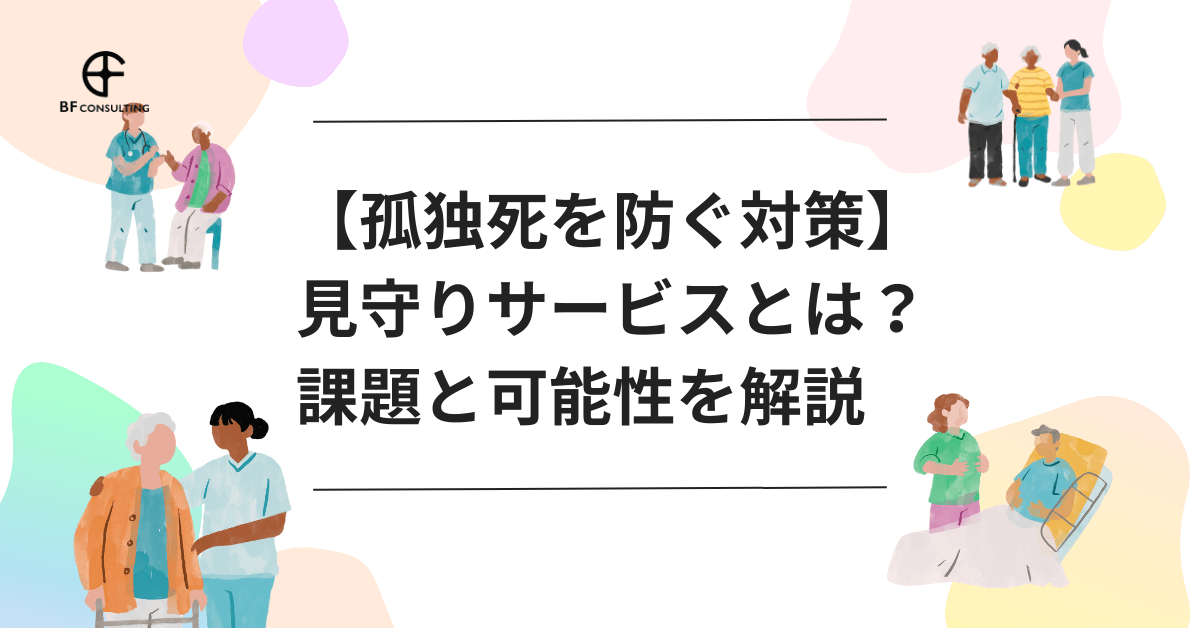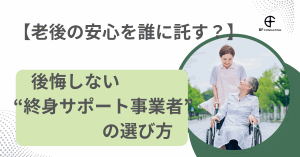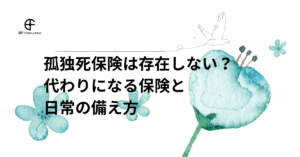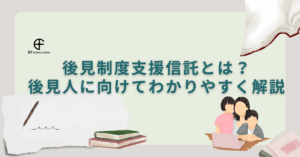いま、日本では孤独死の問題が深刻化しています。
総務省の調査によると、令和2年時点で65歳以上の高齢者人口は約3,603万人。そのうち一人暮らしの高齢者は、男性が約231万人、女性が約441万人にのぼり、年々増加傾向にあります。
出典:総務省行政評価局「一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査」
年間7万人を超える方が一人で最期を迎え、そのうち2万人以上が死後8日以上経ってから発見されているという調査もあります。
そこで近年、注目されているのが「高齢者見守りサービス」です。
センサーやカメラ、通信機器を使って自宅の様子を見守る仕組みや、定期的な電話・訪問連絡によるサービスなど、種類もさまざまです。
こうしたサービスは、高齢者の安全を守るだけでなく、家族の精神的負担を軽減し、孤独死や異変の早期発見にもつながる重要な手段となっています。
今回は、悲しい現実に対する手立てとして注目されている「見守り」について考えてみたいと思います。
高齢者見守りサービスとは?
高齢者見守りサービスとは、高齢者の安全・安心を目的に、日常生活や安否を遠隔で確認する仕組みです。
仕事や距離の都合で家族が定期的に訪問できないケースでも、安否確認や緊急時の対応を可能にする仕組みとして、今大きな注目を集めています。
特に、高齢者の孤立や体調の急変、詐欺や犯罪被害といったリスクが指摘される中、こうしたサービスは事故や異変の早期発見につながり、家族の安心感や負担軽減にも大きく貢献しています。
また近年では、自治体が機器設置費用の一部を補助する取り組みも進んでおり、地域ぐるみの見守り体制が広がっています。センサーやカメラ、通報ボタンなどの見守り機器を活用し、地域・家族・サービス提供者が連携して支える体制が構築されつつあります。
自治体の取り組み事例と実施率
| 見守りネットワークの連携の実施 | 都道府県では43カ所 |
|---|---|
| 認知症高齢者の見守り事業の実施 | 市区町村単位では全体の93%(1,658カ所) |
| 見守りに関するネットワークを構築 | 市区町村単位では全体の86%(1,429カ所) |
こうした背景からも、見守りサービスの需要は年々高まり、今や高齢者の生活支援に欠かせない存在となっています。
高齢者の一人暮らしに潜むリスク
一人暮らしの高齢者(独居老人)が増加する背景には、「配偶者との死別」や「子どもに迷惑をかけたくない」といった事情のほか、「自分のペースで気楽に暮らしたい」といった前向きな理由も見られます。
しかし、高齢者の一人暮らしには、健康・安全・社会的な孤立といった多方面にわたるリスクや課題が潜んでいます。
ここでは、代表的な問題をいくつか見ていきましょう。
孤独死のリスクが高まる
一人暮らし世帯(単独世帯)の増加に伴い、孤独死のリスクも深刻化しています。
日本少額短期保険協会の調査によると、2020年には単独世帯が全体の約4割を占めるまでに増加。
年間7万人を超える方が一人で最期を迎え、そのうち2万人以上が死後8日以上経ってから発見されているという調査もあります。
高齢者が体調を崩しても連絡が取れない・発見が遅れる状況は、社会問題としても注目されています。
病気・ケガ・認知症発症時の発見が遅れる
高齢者の健康状態の変化は、早期に気づくことが重要です。
しかし一人暮らしでは、病気やケガ、転倒などの異変に気づかれにくく、重症化や死亡リスクに直結してしまいます。
また、認知症の初期症状は周囲の指摘がないと見逃されがちです。発症に気づかず生活に支障が出るケースもあり、トラブルの発生にもつながります。
こうした事態を防ぐためにも、見守りサービスや地域のサポート体制の活用が重要です。
社会的孤立と心の問題
高齢者の一人暮らしでは、日常的な会話や人との関わりが大きく減少します。
社会的孤立感や孤独によるストレス・抑うつ状態に悩まされる方も多く、場合によっては自殺のリスクさえあります。
特に、近所付き合いの減少や地域とのつながりの希薄化は、社会的孤立の深刻化を招きます。
見守り体制の整備や、地域コミュニティ・ボランティア活動などの参加機会を増やすことが求められています。
高齢者見守りサービスの種類
大きく分けて以下のようなタイプがあります。
- 訪問型:定期的な訪問による対面確認
- 通報型:緊急ボタンや音声通報装置を使った通知
- センサー型:人感・開閉センサーやスマートメーターによる検知
- アプリ・IoT型:スマホやウェアラブル端末と連携した監視
訪問型・宅配型見守りサービス
訪問型見守りサービスは、専任スタッフが高齢者の自宅を定期的に訪問し、安否確認や健康状態の把握、生活上の相談対応などを行う仕組みです。
近年では、電力会社や水道局の検針員、郵便局員など、地域と関わりの深い企業が見守り活動に参加するケースも増えており、地域ぐるみのサポート体制として注目されています。
一方、宅配型見守りサービスは、食事の配達(配食サービス)や日用品の宅配時に、配達スタッフが高齢者の様子を確認するものです。
配達の際にちょっとした会話を交わすことで、異変の早期発見や心理的な安心感の提供にもつながります。
実際に導入されている例
- 郵便局の「みまもり訪問サービス」
月1回、郵便局員が訪問し、報告書を家族に送付(980円〜) - 自治体の「高齢者見守りネット」
地域住民や店舗が異変に気づいた際に通報する仕組み
通報型見守りサービス
通報型見守りサービスは、高齢者が異変を感じたときや緊急時に、自らの操作で通知を送信できる仕組みです。
代表的な機器には、緊急ボタン(ペンダント型・据置型)や音声通報装置などがあり、自宅に設置されたこれらの装置を押すことで、スタッフや家族、地域の見守りセンターへ即時に通報が届きます。
たとえば、体調の急変や転倒によるケガなど、孤独死や重症化のリスクを防ぐための手段として活用されており、早期対応や救急搬送にもつながる重要な役割を果たします。
操作は非常にシンプルで、高齢者本人でも迷わず使用できる設計になっており、導入コストも比較的低めな点がメリットです。
一部の機器には一定時間動きがない場合に自動通報する機能や、センサーと連動した通報機能も搭載されており、本人の操作が難しいケースにも対応可能です。
実際に導入されている例
- ALSOKの「みまもりサポート」
パネルやペンダントにあるボタンを押すと警備員が駆けつけるシステム(1,870円〜)
センサー型見守りサービス
センサー型見守りサービスは、高齢者の自宅に設置された人感センサーや開閉センサー、スマートメーター(電気・ガスの使用状況)などを活用し、日常生活の行動パターンを24時間体制で見守る仕組みです。
玄関やトイレ、寝室などに設置されたセンサーが、動きの有無や室温の変化を常時検知し、
「一定時間まったく動きがない」「普段とは異なる生活リズムが続く」といった異常の兆候を捉えると、家族やサービス提供者に自動で通知されます。
このシステムは、転倒や体調不良、認知症の進行による行動変化など、本人が気づきにくい緊急事態を早期にキャッチできるのが特長です。
また、カメラを使わずに見守るためプライバシーにも配慮されており、非接触・非侵入型での見守りが可能です。
近年では、冷蔵庫・エアコンなどのスマート家電や、ガス・電気の使用状況と連動させたサービス、さらにはホームセキュリティと統合されたシステムなど、テクノロジーを活用した新たな見守りの形が広がっています。
実際に導入されている例
- auの「かんたん見守りプラグ」
コンセント型のプラグに4つのセンサーが埋め込まれており、動作・電力・照度・温湿度から異常を検知するシステム(8,800円〜)
アプリ・IoT型見守りサービス
アプリ・IoT型見守りサービスは、スマートフォンやウェアラブル端末、IoT機器と連携して、高齢者の健康状態や日常の動きをリアルタイムでモニタリングする見守り方法です。
従来のセンサー型や訪問型と比べて、デジタル技術を活用した柔軟な見守りが可能です。
たとえば、心拍数・歩数・睡眠時間・体温などを記録できるスマートウォッチやヘルスケアアプリを活用すれば、体調の変化や異常の兆候を早期に察知できます。
取得したデータは、専用アプリを通じて家族や介護スタッフに自動通知される仕組みとなっており、遠方に住む家族も安心して状況を把握できます。
また、転倒検知機能や位置情報(GPS)を備えた端末もあり、外出先での事故や徘徊リスクにも対応。必要に応じて緊急通報機能と連動することで、素早い対応が可能となります。
スマホ操作に不慣れな高齢者でも、装着型デバイスや自動送信システムを利用すれば負担が少なく、日常生活を邪魔しない点もメリットです。
また、データの蓄積によって体調の傾向分析や予防ケアにも活用でき、在宅介護や地域包括支援との連携にも役立ちます。
実際に導入されている例
- IoTを活用した見守り
スマートホーム技術と介護支援を組み合わせたサービス
高齢者見守りサービスのメリット
高齢者見守りサービスを利用することで得られる主なメリットは、以下の3つです。
- 健康状態の変化に気づきやすくなる
- 生活リスクの早期発見・予防ができる
- 家族の不安や精神的負担を軽減できる
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
健康状態の変化に気づきやすくなる
高齢者は、持病の悪化や体調の急変が起こりやすく、日々の健康管理が重要です。
見守りサービスを利用すれば、センサーやカメラ、音声機能などを通じて表情や動作を遠隔で確認できるため、離れていても異変に気づきやすくなります。
万が一、体調不良や転倒などの異常があった場合も、自動通知や通報システムによって、医療機関や家族への連絡がスムーズに行える体制が整っています。
生活リスクの把握と予防ができる
高齢者見守りサービスは、日常生活の行動パターンをデータとして把握できるため、生活環境の中に潜むリスクの発見にも役立ちます。
たとえば、「よくつまずく場所」や「夜間の動線の暗さ」などがわかれば、手すりの設置や照明の改善などのバリアフリー対策を計画的に進めることが可能です。
このように、事前に危険を予測し、事故を未然に防ぐ“予防的な介護につなげられるのも大きなメリットです。
家族の不安・精神的負担を軽減できる
遠くに住む家族にとって、一人暮らしの高齢者の様子が見えないことは大きな不安要素です。
しかし、見守りサービスを導入すれば、アプリや通知機能を使って安否をタイムリーに確認でき、精神的な安心感を得られます。
特に遠距離介護をしている方にとっては、センサーによる自動検知や緊急通報システムの存在が心強いサポートとなります。
異変が発生した際には、専門スタッフが現地で初期対応を行うため、家族がすぐに駆けつけられない場合でも対応が可能です。
高齢者見守りサービスのデメリット・課題
多様なサービスがある一方で、以下のような課題も顕在化しています。
- 料金負担や支援制度の格差
- デジタル機器の操作に不安がある
- 誤作動や運用負担のリスク
- サービス選びが難しく、本人の同意も得にくい
料金負担や支援制度の格差
月額3,000〜5,000円程度の利用料は、低所得の高齢者世帯にとって大きな負担となることがあります。
また、自治体による補助制度の有無や内容に地域差があるため、支援の公平性にも課題が残ります。
デジタル機器の操作に不安がある
スマートフォンやIoT機器など、デジタル機器に不慣れな高齢者にとっては、設定や操作がストレスや混乱の原因になることがあります。
誤作動や運用負担のリスク
センサーがペットの動きに反応して誤作動を起こすケースや、本人の生活スタイルに合っていない機器を導入したことで、アラートが頻発し運用の手間が増えるといった課題もあります。
サービス選びが難しく、本人の同意も得にくい
選択肢が多すぎてどのサービスが最適か分からないと感じる家族も多く、本人の理解や同意を得られず導入が進まないケースも見受けられます。
今後の展望と求められる変化
高齢者見守りサービスの導入により、孤独死や体調異変の早期発見といった命に関わるリスクは確実に低減しつつあります。
特に、一人暮らしの高齢者が急増する中で、家族や地域とのつながりが希薄になる現代社会において、見守りの仕組みは必要不可欠なインフラとも言えるでしょう。
しかしその一方で、センサーやカメラ、アプリなどによる見守りに対して、「監視されている」「自由を奪われている」と感じる高齢者も少なくありません。
これはプライバシーの尊重や心理的な配慮が不十分な場合に起こりやすく、今後は本人の意向や生活スタイルに寄り添う仕組みづくりがより一層求められます。
たとえば、常時録画ではなく一定条件でのみ作動するセンサー型の見守りや、本人が見守りの目的と仕組みを理解・納得したうえで利用できる説明体制の強化などが、導入時のハードルを下げる一助になります。
また、今後の理想的な展開としては、単なる「安否確認」にとどまらず、「認知機能の変化」「生活リズムの乱れ」「日常行動の異常」といったより深いレベルでの生活支援へと発展していくことが望まれます。
これにより、認知症やうつ症状の早期発見、転倒・失禁といった生活機能低下の兆候の把握も可能となり、未然に対応できる福祉体制を築けるようになります。
今後求められる社会的支援と制度的変化
高齢者見守りサービスの質を保ち、事業者が継続的に安心・安全な支援を提供するためには、社会全体で支える仕組みが不可欠です。以下のような取り組みが今後さらに重視されるでしょう。
- 公民連携モデルの普及:民間の技術と行政のネットワークを融合
- 補助金や介護保険との併用:実費負担の軽減
- 多世代連携:若者やシングルマザーなどをサポーターとして雇用し、地域に新たな役割を
- 防災連携:災害時の安否確認と避難支援を組み合わせる
1. 公民連携モデルの推進
民間企業の先端技術(IoT、AI、センサーなど)と、行政の地域ネットワークや福祉サービスを融合することで、効果的かつ持続可能な見守り体制を構築することが可能です。
地域包括支援センターや自治体がハブ的な存在となり、見守りを必要とする高齢者に適切なサービスをマッチングするモデルが全国で広がりつつあります。
2. 補助金・介護保険制度との連携
見守り機器やサービスの導入には費用がかかるため、経済的理由で利用を諦める世帯も少なくありません。
そのため、国や自治体による補助金制度や、介護保険との併用可能な仕組みの整備が不可欠です。
こうした支援が進めば、利用者の負担軽減とともに、サービス提供者の運営継続にもつながります。
3. 多世代連携による地域の再構築
見守り支援の担い手として、若年層やシングルマザー、定年退職者などを地域サポーターとして雇用・育成する動きも始まっています。
「支援を受ける人」と「支援する人」が共存できる地域づくりによって、新たなコミュニティの形成と孤立防止の効果が期待されます。
4. 防災との連携
災害時においても、高齢者の安否確認は重要な課題です。見守りサービスのデータは、避難支援や安否把握にも活用できるため、地域の防災体制と連携した統合管理が今後ますます必要となります。
特に気候変動や自然災害の多発に伴い、見守りサービスが持つ多機能性を活かした防災・減災への展開が注目されています。
孤独死を防ぐ"やさしいみまもり"のあり方
「見守り」は、遠く離れて暮らす家族の“目”となり、高齢者の暮らしに安心とつながりをもたらす存在です。かつて同居が当たり前だった時代には、「顔色」「受け答えの変化」「生活音」などから家族が自然に気づき、支えてきました。
しかし現代は、核家族化や地域とのつながりの希薄化が進み、そうした“気づき”が難しくなっています。
だからこそ今、テクノロジーによる見守りだけでなく、「人の手」「地域の目」「行政の支援」を融合させた、“やさしい見守り”のあり方が求められています。
大切なのは、見守りそのものが目的になるのではなく、高齢者が住み慣れた場所で、自分らしく、安心して暮らし続けるための自然な支えであること。
見守りは押しつけるものではなく、「あなたはひとりじゃない」と伝える、そっと寄り添う社会のまなざしであるべきです。
孤独死や健康不安を防ぎ、心の孤立をも支える見守り体制を、家族・地域・社会全体で共に築いていく..
そんな“やさしいみまもり”のあり方を、社会全体で考えていく必要があると感じます。