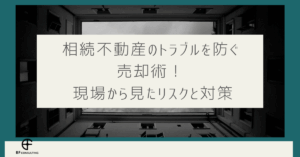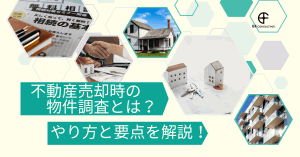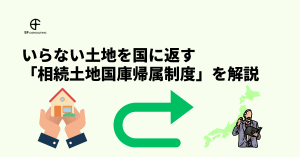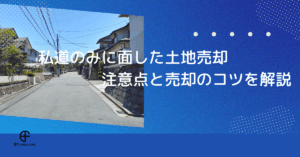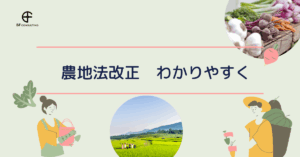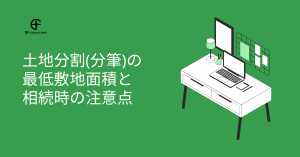市街化調整区域の開発許可をわかりやすく解説します。
市街化調整区域は、無秩序な市街化を抑制するため、原則として開発行為・建築は不可です。
ただし、都市計画法34条の立地基準(1号~14号+8号の2)に該当すれば、一定の条件のもとで例外的に許可が下ります。
ポイントは、「どの区域に」「どんな用途を」「どの規模で」「誰の生活・事業のために」行うのか。さらに、条例運用(都道府県・市町村)やインフラ(道路・上下水道)、周辺環境、用途地域・地区計画との整合が審査の肝になります。
本稿では、34条各号の条文概要・主な用途・自治体運用事例・許可条件を具体的に解説し、農地転用や資材置場、分家住宅、沿道サービス、既存集落の区域指定など実務でつまずきやすいケースを申請の流れ・注意点・費用負担の目安と併せて整理します。
相続・売却・査定での価値判断(しんしゃく割合)も実務目線でチェック。
まずは区域区分の確認→事前相談→必要書類の整備という基本から押さえましょう。
都市計画法第34条の要件を満たせば開発許可が認められる
市街化調整区域は原則として開発行為が禁止されていますが、都市計画法第34条では一定の要件のもと例外的に開発許可が認められる「立地基準」が定められています。
第34条各号(第1号~第14号)は、市街化調整区域内で許可され得る開発行為の類型を列挙したものであり、無秩序な市街化の防止と地域の実情に応じた必要最小限の開発を両立させることを目的としています。
2023年には第8号の2が新設され、現在は「1号~14号(8号の2を含む)」の計15区分の立地基準が存在します。
都市計画法とは?
都市再開発法は、老朽化した建物が密集する市街地を再整備し、土地の有効活用と都市機能の向上を図ることを目的として、1969年(昭和44年)に制定され、市街地再開発事業の制度が定められました。
都市計画法第1条では、以下を目的と定められています。
(目的)
都市計画法 第一条(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
市街地再開発事業を行う際に、まず確認すべき重要なポイントは、その土地が「市街化区域」なのか「市街化調整区域」なのかという点です。
なぜなら、市街化調整区域では、原則として新たな建物の建築や開発行為が認められていないためです。
つまり、基本的に市街化調整区域内での開発は許可されません。
ただし、都市計画法第29条で定められた「開発許可の除外規定」に該当する場合は、許可を受けずに開発できるケースもあります。
さらに、除外規定に該当しない場合であっても、一定の条件を満たす「特例要件」に該当すれば、例外的に開発が許可されることがあります。
この特例の根拠となるのが、都市計画法第34条に定められた立地基準です。
以下の表に、第34条各号ごとの条文概要、主な開発用途の例、実際の許可事例(自治体での運用例)、および許可条件・制限をまとめます。
その後に各号ごとの詳細な解説を記載します。
都市計画法第34条各号の立地基準まとめ
都市計画法第34条には、市街化調整区域において例外的に開発・建築が認められるケースが、1号から14号(および8号の2)まで詳細に定められています。
これらの規定は、あくまで「原則:市街化抑制」の立場を前提とした限定的な特例であり、用途・立地・規模・公益性などの条件をすべて満たす場合にのみ適用されます。
以下の表では、それぞれの条文の概要、主な開発用途、実際の許可事例、そして許可にあたって求められる主な条件や制限を整理しました。
自治体によって運用基準や条例が異なるため、同じ号であっても許可される範囲に差が生じる点には注意が必要です
調整区域内での開発や建築を検討する際は、この一覧を参考にしながら、どの号に該当する可能性があるかを事前に把握しておくことが、円滑な許可取得への第一歩となります。
| 号 | 条文の概要 | 主な開発用途の例 | 許可(自治体運用)事例 | 開発許可の主な条件・制限 |
|---|---|---|---|---|
| 都市計画法第34条第1号 | 地域住民の日常生活に必要な公益的施設・日用品供給施設の建設 | 保育所、学校(一部のみ)、診療所、社会福祉施設、郵便局窓口、コンビニ、理美容店、自動車修理工場、ガソリンスタンド等 | 地域の既存集落内にコンビニエンスストアや小規模店舗が許可された例(いわゆる「一号店舗」) | 周辺の既存集落の住民を主なサービス対象とすること。立地は既存集落内または隣接地に限る。施設規模に制限あり(大規模店不可)。 |
| 都市計画法第34条第2号 | 地域の鉱物資源・観光資源その他の資源の有効利用に必要な施設の建設 | 鉱物資源利用施設(セメント工場等)、観光資源活用施設(展望台、宿泊施設、休憩施設等) | 観光地における展望台や鉱山跡地での採石関連施設の許可事例など | 資源の現地有効活用上必要なものに限る。観光施設は当該資源の鑑賞に必要なものに限る。 |
| 都市計画法第34条第3号 | 特殊な温度・湿度等の条件を必要とし、市街化区域内で建設困難な事業用施設 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 都市計画法第34条第4号 | 農林漁業用建築物および地場産物の処理・貯蔵・加工に必要な施設の建設 | 農水産物加工場(野菜・果実の缶詰工場、製粉業施設、醸造施設、飼料工場、製茶工場、製材所等) | 農産物の集荷場やワイナリー施設等が許可された事例 | 地場産物を産地で迅速に処理・加工する必要があるものに限る。純然たる農林漁業従事者向け施設や地場産業振興目的の施設が対象。 |
| 都市計画法第34条第5号 | 特定農山村法※に基づく土地権利移転計画で定められた活性化基盤施設の建設 (特定農山村法: 特定農山村地域の農林業等活性化基盤整備促進法) | 農林業等活性化基盤施設 | (特定法に基づく限定的事例のみ) | 当該特定農山村地域の計画公告に基づき、計画で定められた土地に計画どおりの基盤施設を建設する場合に限る。一般の開発には適用されない特例。 |
| 都市計画法第34条第6号 | 都道府県と中小企業基盤整備機構が助成する、中小企業の連携・集積活性化事業用施設の建設 | 中小企業共同利用施設(地方公共団体と中小企業基盤整備機構の助成対象施設) | 中小企業団地等で共同工場を整備した例 | 都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構が一体となって助成する事業に限る。該当事業計画の認定が必要。 |
| 都市計画法第34条第7号 | 市街化調整区域内の現存工場に密接関連する事業用施設の増設 | 既存工場の関連施設 | 既存工場敷地に隣接して物流棟を増築した例など | 当該事業が現にある工場と密接に関連し、活動効率化のためどうしても調整区域内に増設が必要なもの。立地は既存集落内またはその隣接地に限る。 |
| 都市計画法第34条第8号 | 危険物の貯蔵・処理のための施設で、市街化区域内で建設することが不適当なものの建設 | 火薬庫、危険物倉庫等 | 採石場における火薬庫設置の許可例など | 政令で定める危険物施設に限る。市街化区域では安全上不適切なもののみ許可対象。 |
| 都市計画法第34条第8号の2 | 災害危険区域等(レッドゾーン等)にある既存建築物を調整区域内の安全な場所へ移転する開発行為(※2023年施行の新設規定) | (個別用途ではなく既存建物と同用途の移転)住宅、工場等の既存建築物の代替建設 | 土砂災害特別警戒区域内の住宅を近隣の安全地に移築した例 | 移転元建物: 違法建築物でないこと、令和4年4月1日時点(基準日)以前から存在すること、移転後に速やかに除却すること等。移転先: 用途は元建物と同一、延べ面積・敷地は元の1.5倍以内(戸建住宅は延べ200㎡/敷地500㎡まで特例)、同一市街化調整区域内で市町村の土地利用計画に適合する場所、原則幅員4m以上の道路に接道すること等。 |
| 都市計画法第34条第9号 | 上記各号以外で、市街化区域内で建設困難または不適当な施設として政令に定めるものの建設 | 沿道サービス施設(道路管理施設、休憩所〈ドライブイン〉、給油所〈GS・LPG・EV・水素スタンド等〉)、火薬類製造所など | 高速道路IC付近にドライブイン(休憩所)やガソリンスタンドが許可された例 | 政令指定の施設のみ対象。例えば休憩所は高速道路等の適切な位置に設置されるものに限り、駐車場を席数に応じ確保する等の基準あり。沿道サービス施設は運転者休憩目的に限られ、物販主体のコンビニ等は含まない。事業者自ら運営する施設のみ許可(賃貸目的の店舗不可)。 |
| 都市計画法第34条第10号 | 地区計画または集落地区計画(整備計画あり)区域内で、当該計画に適合する建築物の建設 | 地区計画区域内の住宅、共同住宅、長屋、小規模店舗等 | ○○市における集落地区計画で定められた住宅団地の開発許可例など | 当該地区計画・集落地区計画で建物用途や配置が定められていること。計画の内容に適合する建築計画であること。区域は整備計画が定められたものに限る。 |
| 都市計画法第34条第11号 | 市街化区域に近接し生活圏を一体にする50戸以上の既存集落について、条例で指定した区域内での開発(一定用途を除く) | 条例で指定された既存集落の区域内での住宅、共同住宅、長屋、小規模店舗等 | 多くの自治体で「既存集落の区域指定」により自己用住宅の建築を許可(例:鹿児島市では11号区域を既存集落中心に限定するよう条例運用を見直し) | 市街化区域に隣接/近接し自然・社会条件から一体的生活圏を構成する既存集落で、おおむね50棟以上が連坦している地域を対象に都道府県等が条例指定。条例で環境保全上支障となる用途を除外指定し、それ以外の用途の自己用建築等を許可。区域・用途は各自治体の運用により異なる。 |
| 都市計画法第34条第12号 | 市街化を促進せず市街化区域内での実施困難と認められる開発行為で、政令基準に従い都道府県条例で区域・目的・用途を限定して定めるもの | 分家住宅、既存集落内自己用住宅、公共事業代替施設、災害危険区域からの移転住宅、自治会集会所、防災倉庫等 | 各地で農家の子息が親元近くに住宅を建てる「分家住宅」の許可事例が多い。他に区画整理事業の代替住宅や防災集会所の整備例など。 | 都道府県条例で個別に定める類型のみ許可。多くは属人要件あり:例として分家住宅は「長年調整区域に居住する世帯から独立する親族が、本家近くに自己用住宅を建てる場合」等が該当。申請者が本家の親族であること、既に自己住宅を持たないこと、都市計画区域内に代替地を持たないこと等厳しい条件あり。用途や区域も条例で限定。 |
| 都市計画法第34条第13号 | 区域区分決定または調整区域拡大時に土地所有権等を有していた者が、自己用建築の目的で決定後6か月以内に届出をした場合の既得権行使による開発 | 区域指定時に届出された自己用住宅・事業用建築物 | 調整区域拡大(線引き変更)時に、既に土地を所有し将来建築予定だった者が権利申出を行い住宅を建築した例 | 区域区分の決定・変更日から6か月以内に所定事項を知事に届け出ていること。対象者はその決定時に当該土地の権利を有していた個人・法人に限られる。許可期間は届け出から5年以内(猶予措置)。自己の居住・業務用に供する建築物に限る。 |
| 都市計画法第34条第14号 | 上記各号に該当しない開発行為で、開発審査会の議を経て市街化促進のおそれがなく市街化区域内で実施困難と知事が認めるもの(いわゆる「開発審査会基準」) | 社寺・仏閣、納骨堂、研究施設(調整区域内対象の研究に必要なもの)、従業員用社宅・寮、公営住宅、既存建物の建替え・増築、都市内災害危険地区からの建物移転、レクリエーション施設、既存集落内の小規模工場、特定物流施設、社会福祉施設、長期利用建物の用途転換、定住促進の賃貸住宅転用、地域産業振興施設 等 | 開発審査会付議の個別許可事例多数。例:郊外に工場従業員向け社宅を建設、寺院の郊外移転、新設大学の実験施設建設、大規模物流倉庫の建設許可(福岡市東区でも物流センターが調整区域に建設)など。 | 都道府県知事が開発審査会の議決を経て個別許可。周辺の市街化を誘発しない立地であること、市街化区域内で代替が著しく困難な公益性・必要性の高い開発であることが求められる。案件ごとに用途・公益性・周辺環境への影響を審査。許可にあたって条件(例:必要最小の規模、既存建物除却、用途限定など)が付されることが多い。 |
(※表中の特定農山村法=「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」)
都市計画法第34条各号の詳細をわかりやすく解説
ここからは、都市計画法第34条の各号について、実務でつまずきやすい「対象用途・許可されやすい場面・注意すべき条件」をわかりやすく解説します。
原則はあくまで市街化抑制ですが、生活インフラの確保や地域資源の活用、防災上の必要性など、例外が認められる余地は号ごとに異なります。表では条文のねらいを一言で押さえたうえで、代表的な用途例、各地の運用事例、そして実際の審査で重視される主な条件・制限を横並びで確認できるようにしました。
まずは「どの号に乗せられそうか」を当たり付けし、該当しそうな号の注意点を読み込みながら、早期の事前協議や条例確認につなげてください。
自治体ごとに解釈や基準が細かく異なるため、同じ用途でも適否が分かれる点に留意し、個別案件では必ず最新の運用と技術基準を前提に検討を進めることが肝要です。
都市計画法第34条第1号:公益上必要な建築物・日常生活施設
都市計画法第34条第1号:公益上必要な建築物・日常生活施設について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
調整区域内において周辺住民の健全な日常生活に必要な公益的施設や日用品供給の店舗・事業所の建築が対象です。
いわゆる「一号店舗」と総称され、市街化調整区域の既存集落の生活維持に不可欠な施設が許容されています。
主な用途例
保育所、幼稚園などの児童施設や一部の学校、診療所・助産所、デイサービス等の社会福祉施設、郵便局窓口、銀行・保険窓口、コンビニエンスストア、理美容店、コインランドリー、自動車整備工場、ガソリンスタンド、プロパンガス販売所、農協の店舗・農機具修理施設、飲食店(食堂・レストラン・喫茶店等)など。
これらは周辺住民が日常利用する小規模な施設が中心で、特に日用品店などは「一号店舗」と呼ばれます。
許可事例
地域の集落に日用品店やコンビニを新設したケースがあります。
例えば〇〇市では、最寄りの商業施設が遠い調整区域の集落内にコンビニエンスストアの建設が一号許可された例があります(地域住民向けサービスに特化した小規模店舗)。
他にも、長年無医地区だった集落に診療所が許可された事例など、生活インフラ確保の観点から許可されるケースが見られます。
許可条件
いずれも「周辺の調整区域居住者を主たるサービス対象とすること」が必須です。
立地は既存集落内またはその隣接地に限られ、孤立した場所への建設は認められません。さらに施設規模にも制限があり、地域の需要からかけ離れた大規模店舗などは許可されません。
条例で延床面積や敷地面積上限を定める自治体もあります。また、類似の小規模店舗で延べ50㎡以下・営業床面積が半分以下等の一定条件を満たす場合には、開発許可自体が不要となる特例もあります(極めて小規模な自営店舗は許可対象ではなく許可不要扱い)。
都市計画法第34条第2号:資源の有効利用上必要な建築物
都市計画法第34条第2号:資源の有効利用上必要な建築物について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
調整区域内に存在する鉱物資源や観光資源その他地域資源を有効活用するために必要な建築物(または第一種特定工作物)の建設を目的とする開発行為です。
主な用途例
採石場・鉱山におけるセメント工場などの鉱物資源処理施設、景勝地における展望台・観光客用宿泊施設・休憩所などの観光資源活用施設が代表例です。
その他、水源地の水処理施設や地熱発電関連施設など「その他の資源」を活かす施設も政令で定められれば該当し得ます。
許可事例
鉱物資源系では、実際に鉱山跡地の調整区域内に砕石処理プラントを新設した例があります(市街地では環境上困難なため第2号許可)。
また観光系では、都市近郊の山間部(調整区域)において景観を楽しむための展望台や郷土資料館を建設した許可事例が見られます。
これらは観光客誘致による地域振興を図りつつ、市街地では適地がないため調整区域内に特例的に認められています。
許可条件
該当施設がその資源の現地利用に不可欠であることが条件です。
例えば観光施設であれば、その土地の自然・文化資源の鑑賞や保全に必要なものでなくてはなりません。市街化区域内で代替可能な単なる娯楽施設などは認められません。
また、鉱物資源施設の場合もその鉱区での採取・処理上必要だからこそ許可されるのであり、他地域から原料を運び込む大規模工場は想定されていません。
環境影響への配慮や景観対策も求められ、必要に応じて環境アセスメントや周辺住民の同意など追加条件が付されることもあります。
都市計画法第34条第3号:特殊条件下で市街化区域内建設が困難な事業用建築物
都市計画法第34条第3号:特殊条件下で市街化区域内建設が困難な事業用建築物について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
温度・湿度・空気など特殊な環境条件を必要とする政令指定の事業用建築物または特定工作物で、その特殊条件ゆえ市街化区域内で建設が困難なものを対象とした規定です。
主な用途例
(現在のところ政令未制定のため具体的対象なし)法律上は例えば高度な気象条件や地盤条件が必要な研究施設・実験施設などが想定されていました。
しかし、本号に該当する政令が制定されていないため、該当する施設は存在していません。
許可事例
実質的な運用例はありません。制定以来、この条項を直接適用して許可されたケースはないとされています。
特殊条件を理由にした開発は、実際には必要性があれば第14号(個別審査)で対応されてきました。
許可条件
仮に政令指定があれば、その特殊条件が当該地でしか満たせない必然性が求められるでしょう。
市街化区域で通常は確保できない特殊環境(例えば高湿度空間や特殊な気流環境など)の必要性を証明することが必要になります。現時点では制度上空文化している条項ですが、社会情勢の変化で必要になれば政令制定される可能性もあります。
都市計画法第34条第4号:農林漁業用建築物・地場産品の処理加工施設
都市計画法第34条第4号:農林漁業用建築物・地場産品の処理加工施設について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
調整区域内で行われる農業・林業・水産業の用に供する建築物(ただし農作業用倉庫など法29条1項2号で許可不要とされるものを除く)や、調整区域内で生産される農産物・林産物・水産物の処理・貯蔵・加工に必要な建築物を対象としています。
主な用途例
地元産品の加工工場や倉庫が典型です。具体的には、畜産物処理施設、漁業の水産物加工場、野菜・果実の缶詰工場、農産物の漬物工場、製茶工場、製粉工場、食用油の精製工場、飼料工場、製材所など、多岐にわたる食品・木材加工関連施設が含まれます。これらはいずれも産地で速やかに処理する必要のあるものです。
許可事例
農村地域でのワイン醸造所やクラフトビール醸造所が許可された例があります。葡萄の産地にワイナリー(醸造所)を造り、その場で製品化することで地域ブランド化を図るといったケースです。
また、漁港近くの水産加工場(干物加工場など)が第4号許可で建設され、水揚げ直後の加工を可能にした例もあります。いずれも産地ならではの即時加工・出荷が求められる施設でした。
許可条件
キーワードは「産地性」です。本号で許可されるのは、その地域で産出した農林水産物を速やかに処理・加工・保存する必要がある施設に限られます。
例えば大都市向けの商品製造工場のように原料を他地域から集める施設は対象外です。また農林漁業の付随施設であっても、単なる営業倉庫や流通センター的なものは第4号には該当せず、第14号で個別審査となります。規模についても地域の生産量に見合った適正規模に限るとされ、過大な設備投資は抑制されます。
環境面では排水や悪臭対策など公害防止措置も許可の前提となります。
都市計画法第34条第5号:特定農山村地域における活性化基盤施設
都市計画法第34条第5号:特定農山村地域における活性化基盤施設について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
**特定農山村地域の活性化基盤整備促進法(平成5年法律第72号)**に基づく所有権移転等促進計画で定められた農林業等活性化基盤施設の建設を目的とする開発行為です。
簡潔に言えば、過疎の農山村で市町村が策定する計画に沿って集落の土地利用を再編し、必要な拠点施設を整備する場合の特例です。
主な用途例
上記法律で定義される農林業等活性化基盤施設が該当します。
例えば、農山村の振興のために計画された集落センターや農産物直売所、農業研修施設、体験交流施設などが挙げられます(具体例は当該地域の計画内容によります)。
許可事例
全国的にも数が少ないですが、一例として〇〇県△△村では、特定農山村法に基づく計画により分散していた農家を集住化し、その拠点に農業支援センター(農機具の共同利用施設や加工施設)を建設したケースがあります。
この施設建設が第5号に該当し、許可が下りています。
許可条件
法定計画に明示された施設に限られます。つまり、その市町村が国の承認を得て公告した所有権移転等促進計画において「ここに○○施設を建てる」と決めている場合のみ許可されます。
したがって一般の開発許可申請で第5号を適用することはできません。また、対象地域も「特定農山村地域」に限定されます。計画の有効期限や目標達成状況も考慮され、計画変更があれば許可は困難になります。
都市計画法第34条第6号:中小企業の連携・共同化促進事業施設
都市計画法第34条第6号:中小企業の連携・共同化促進事業施設について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
都道府県が国または独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する、中小企業者の連携・共同化事業や集積活性化事業の用に供する建築物等の開発行為が対象です。
中小企業の競争力強化のための共同施設に道を開く規定です。
主な用途例
典型例は中小企業者の共同利用施設です。例えば、中小企業の組合が共同で利用する部品工場や流通センター、共同作業所、研修施設などが考えられます。
また、複数の地元中小企業が出資して建てる共同物流倉庫や商業共同店舗なども該当し得ます。
許可事例
かつて高度経済成長期には、地方自治体が中小企業団地を造成し、組合主体で工場団地を整備した例があります。
〇〇県××市では、中小企業等協同組合法に基づく組合が調整区域内の工業団地に共同工場を建設し、第6号適用で許可を得ました。
また、県が中小企業庁系の補助を受けて設置した中小企業研修センターが第6号許可となったケースもあります。
許可条件
行政の助成制度と連動していることが絶対条件です。具体的には、都道府県と中小企業基盤整備機構等が一体で助成する事業に位置付けられていなければなりません。
そのため、単に中小企業が集まる計画では適用されず、公的支援策の対象事業である必要があります。
また、共同化・集積による経済効果や公益性も審査されます。立地については既存の工業集積に近接した場所が選ばれる傾向にあり、インフラ条件や環境対策も求められます。
都市計画法第34条第7号:既存工場に関連する事業用施設
都市計画法第34条第7号:既存工場に関連する事業用施設について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
調整区域内ですでに稼働中の工場施設における事業と密接な関連を有する事業用建築物(または特定工作物)で、それらの事業活動の効率化のため調整区域内での建設が必要なものの開発行為が対象です。
要するに、「既存工場のサテライト施設」を想定した規定です。
主な用途例
既存工場の関連施設とされ、具体例としては工場の製品を保管・出荷するための倉庫、関連会社の部品工場や実験棟、製造工程の一部を受け持つ下請工場、従業員の福利厚生施設(社宅や寮、研修所)などが挙げられます。
ポイントは既存工場と一体的に機能する施設であることです。
許可事例
実例として、調整区域内に古くから立地する工場Aに隣接して、その製品の物流センターを新設したケースがあります。これは工場Aから直接製品を搬入でき物流効率が上がるため第7号で許可されました。
また、工場設備の老朽化に伴い隣地に新工場棟を建て替え、旧工場を倉庫化するプロジェクトも関連施設とみなされ許可された例があります(既存工場の機能更新)。
許可条件
既にその場所に工場が存在していることが大前提です。新規に工場誘致する場合には使えない規定で、あくまで既存工場ありきの特例です。また、建設場所は既存集落内またはその隣接地に限られます。
これは工場が孤立地にポツンとある場合、その周辺一帯の開発につながりかねないため、既存集落の一部として増設する範囲に限定する趣旨です。
さらに、新施設の用途は既存工場の事業と密接不可分であることが必要です。単に同じ企業の別事業では不可で、既存工場の工程の延長線上にある設備であることが求められます。環境への追加負荷(騒音・振動・排水等)がある場合は対策計画の提出や地元説明も必要です。
都市計画法第34条第8号:危険物の貯蔵・処理施設
都市計画法第34条第8号:危険物の貯蔵・処理施設について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
政令で定める危険物の貯蔵または処理に供する建築物・工作物で、かつ市街化区域内で建設することが不適当と政令で定めるものの建設を目的とする開発行為が対象です。
危険性ゆえに市街地には置けない施設を郊外に認める条項です。
主な用途例
代表例は火薬庫です。火薬類取締法で定める火薬庫など、高エネルギー物質を保管する施設は人口密集地には不適切なため、調整区域に設ける余地が与えられています。
また、毒劇物や高圧ガスの大容量貯蔵施設、産業廃棄物の焼却・最終処分場なども政令指定されれば該当となり得ます(※現行では産廃処分場は別途2種特定工作物として許可不要扱い)。
許可事例
採石場での火薬庫設置は典型的事例です。山間部の採石現場に火薬庫を新設する際、第8号許可で対応したケースがあります。
また、過去には火薬類の製造所(試薬工場)が人里離れた調整区域に許可された例も報告されています。いずれも周辺への危険を考慮して市街化区域外を選定したものです。
許可条件
政令で具体的に施設の種類が指定されている必要があります。火薬庫については火薬類取締法上の許可が別途必要なこともあり、立地は人家から一定距離を離す、安全遮蔽土堤を設ける等の基準が細かくあります。
許可にあたっては防災上の観点が最重視され、防火・防犯計画の提出や消防の同意が条件となります。
また、市街化区域内で不適当であること、つまり代替地が市街地に無いことが明白である必要があります。危険物施設は地域住民の理解も必要なため、事前説明や必要に応じて公聴会開催など厳格な手続きを経る場合もあります。
都市計画法第34条第8号の2:災害危険区域内の既存建築物の移転(新設特例)
都市計画法第34条第8号の2:災害危険区域内の既存建築物の移転(新設特例)について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
令和4年法改正で追加された新たな特例で、調整区域内の災害危険区域等(いわゆるレッドゾーンなど開発不適区域)にある既存建築物を、安全な調整区域内の別の場所に移転再建する開発行為が対象です。災害リスクの高い場所からの居住・施設移転を促進する目的があります。
主な用途例
個別用途と言うより「移転再建」がキーワードです。例えば土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に昔から建つ住宅を、近隣の高台の土地(調整区域)に移して建て直すケースがこれに該当します。
他にも洪水浸水想定区域内の工場を、水害リスクの低い調整区域の用地に移転する場合など、元の建物と同じ用途での再建が許可されます。
許可事例
制度新設後徐々に運用例が出始めています。一例として▲▲県では、急傾斜地崩壊危険区域にあった住宅を、区域外の町有地に移築する開発許可が下りました。旧宅は解体され、住民は安全な場所で暮らせるようになっています。
また、洪水常襲地域から公共施設(コミュニティセンター)を移転新築した例も報告されています。いずれも第8号の2の趣旨に沿った「命を守るための移転」です。
許可条件
元の建築物(従前建築物)と新たに建てる建築物(予定建築物)の両面で詳細な要件があります。主な条件は以下のとおりです。
- 従前建物に関する条件: 違法建築物でないこと(適法に建てられた建物であること)、その建物が所在する土地が令和4年4月1日またはそれ以降に災害危険区域等に指定された場合は、その基準日までに建築されていたこと(基準日以降に建てられたものは対象外)。移転後は速やかに元の建物を除却すること(更地にして危険を除去する義務)。元建物の所有者と新建物の所有者が異なる場合は連名で申請すること。過去に同様の移転許可を受けていないこと(1回限り)。
- 予定建物に関する条件:用途は元と同一であること。延べ面積・敷地面積は原則として元の建物の1.5倍以内(ただし戸建住宅の場合は特例で延べ200㎡以下かつ敷地500㎡以下まで認める。新たな敷地は同一の都市計画区域内の調整区域であること。そしてその市町村の土地利用計画や周辺状況と整合しており、市町村長の意見書が添付されること。仮に開発許可が面積要件上不要な場合であっても、技術基準適合のため原則4m以上の道路に接する敷地であること。高さは元建物以下(元が10m未満なら新建物は10mまで可)。…等、大変細かい要件があります。
補足
この第8号の2により、第12号や第14号で個別対応していた災害危険区域からの建替え移転が明文化されました。
移転元が調整区域内でなく市街化区域内の危険地にある場合は、本特例ではなく第14号(災害危険地区からの移転)で扱う点に注意が必要です。
都市計画法第34条第9号:市街化区域で不適当または困難なその他の政令施設
都市計画法第34条第9号:市街化区域で不適当または困難なその他の政令施設について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
上記第1号~第8号(+8号の2)に該当しない建築物・工作物のうち、市街化区域内で建設することが困難または不適当なものとして政令で定めるものを対象とする開発行為です。
要は、都市内に置けない特殊施設を郊外に立地させるための包括規定です。
主な用途例
現行の政令指定例としては大きく二種あります。
一つは道路沿道サービス施設で、高速道路等の沿道に設けられる道路管理施設(維持基地など)や休憩所(ドライブイン的施設)、給油所(ガソリンスタンド、LPG・CNG・水素スタンド、EV充電施設等)が含まれます。
もう一つは火薬類製造所です。他にも将来的に都市内不適とされる施設があれば政令追加され得ます。
許可事例
代表的なのは高速道路のサービスエリア(SA・PA)です。高速道路の休憩所・給油所は多くが市街化調整区域内に立地しており、第9号に基づく開発許可が与えられています(食堂・トイレ・GS等の建物)。例えば△△自動車道◇◇IC付近の休憩施設は第9号許可で設置されました。
また、地方の主要道沿いに大型トラック向けのドライブインやトラックステーションが許可されたケースもあります。火薬類製造所に関しては稀ですが、過去に火工品工場を山中に新設した例があり第9号適用となりました。
許可条件
政令指定された用途でなければ適用不可です。沿道サービス施設の場合、さらに都道府県の運用基準で細かな条件が定められています。
例えば休憩所は「自動車運転者の休憩のための施設」に限られ、宿泊機能は不可、規模も適切な小規模に限定されています。席数に応じた駐車場(おおむね座席4に対し1台)が必要など具体的基準があります。
また、休憩所内に物販主体の店舗(コンビニ等)を併設することは認めない自治体もあります。給油所も高速道や主要道に面し交通の円滑に資する位置であることが求められます。
さらに沿道サービス施設はいずれも自家営業(自己の業務用)のものに限られ、貸店舗的な施設は不可です。火薬類製造所については、安全距離の確保や周囲の土地利用状況から見て都市内立地が不適当であることを厳密に判断します。第9号全般に言えるのは「都市に本来あるべき施設ではない」ことが明確でなければならず、その点の立証が許可上重視されます。
都市計画法第34条第10号:地区計画・集落地区計画に適合する建築物
都市計画法第34条第10号:地区計画・集落地区計画に適合する建築物について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
調整区域内でも、市町村が定めた地区計画または集落地区計画の区域(地区整備計画が定められているもの)において、その計画内容に適合する建築物・工作物の建設を目的とする開発行為が対象です。
地域の計画的な土地利用誘導策に沿った開発を許容する規定です。
主な用途例
地区計画で許容された用途であれば、戸建住宅や共同住宅(アパート)、長屋、小規模店舗、作業場など様々です。
例えば「〇〇地区田園住居地区計画」に基づき一定の広さの住宅のみ建築可とされた区域では、そのルール通りの住宅が建てられます。
また「△△集落地区計画」で定めた生活サービス施設(小さな診療所や店舗など)があれば、それも対象になります。
許可事例
農村集落の計画的な維持を目的に、集落地区計画を策定して若干戸の住宅増築を認めた自治体があります(例:◇◇市□□地区)。この地区では計画策定後に数件の新築住宅が第10号許可で建設されました。
また、ニュータウン計画の未着手地が調整区域となっていた地域で、新たに地区計画を定め小規模宅地開発を許可したケースもあります。いずれも計画で定めた範囲・戸数内での開発に限られています。
許可条件
地区計画(または集落地区計画)が有効に定められていることが前提です。その区域・内容は都市計画決定されている必要があります。
さらに整備計画の内容(用途地域的な指定や建ぺい率容積率、建築面積の制限など)に適合していなければ許可されません。言い換えれば、計画の想定外の建築は不可です。また区域外への越境開発も当然認められません。地
区計画の運用は自治体に委ねられる部分が大きく、許容用途を広く設定して調整区域を実質的に市街化させないよう、計画策定段階で国・県と協議が行われています。第10号許可は「計画通りならOK」という明確さがありますが、逆に計画変更がない限り想定外のものは一切許せない点に注意が必要です。
都市計画法第34条第11号:既存集落の区域指定による開発許可
都市計画法第34条第11号:既存集落の区域指定による開発許可について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
市街化区域に隣接または近接し、自然的・社会的条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している概ね50戸以上の建物が連坦する既存集落について、都道府県(指定市等含む)が条例でその土地の区域を指定し、その指定区域内で一定の用途の建築を認める開発行為が対象です。
通称「区域指定型」とも呼ばれる制度です。
主な用途例
多くの自治体では、指定区域内での自己用住宅の建築を主な対象としています。
つまり指定された既存集落に住む人やその家族が、新たにマイホームを建てたり、建替えしたりする行為です。
また、地域の生活利便に資するような小規模店舗や事業所を含めて許可するケースもあります。ただし条例で環境保全上支障となる用途(例:工場、パチンコ店、ラブホテル等)を除外しているため、基本的には住宅・兼用住宅や小さな店舗程度に限られます。
許可事例
区域指定例は各地にあります。例えば△△県□□市では市街地近郊の5集落を11号区域に指定し、過去10年間で20件以上の住宅建築許可が下りています。
逆に◇◇県▲▲市では、指定区域外の集落での新築を抑制するため、11号区域を既存宅地の密集地域に限定する条例改正を行いました(無秩序な拡散防止)。
また、指定区域内において地元商店の建替えを許可した例もあります(周辺環境に悪影響のない既存店舗の更新として)。
許可条件
区域指定の前提条件として「おおむね50以上の建物が連たん」「市街化区域に隣接/近接」「一体的な日常生活圏」が要件です。この基準に該当する地域のみを対象に、都道府県や政令市が条例で区域指定を行います。
指定にあたっては地域の将来像や農地・自然保全との調和を考慮し、どの集落を指定するかは各自治体で方針が異なります。許可条件としては、指定区域内であっても条例で定める除外用途に該当しないこと(例えば条例で工場は禁止としていれば工場建設は不可)、そして自己用目的であることが多いです。
第11号許可の住宅は属人的ではなく、転売後も建替え可能なケースが多いですが、その分エリアが限定されます。自治体によっては「長年居住者のみ対象」「公共上下水道利用区域のみ指定」等の独自要件を付す場合もあります。
都市計画法第34条第12号:条例で定めるその他の開発行為(分家住宅等)
都市計画法第34条第12号:条例で定めるその他の開発行為(分家住宅等)について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
市街化調整区域内でも市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為について、政令の基準に従い都道府県が条例で区域・目的・予定建築物の用途を限って定めたものが対象です。
平たく言えば、各自治体が地域の実情に応じて条例で認める独自の許可メニューです。
主な用途例
最も一般的なのが分家住宅と呼ばれる農家の子弟等の自己住宅です。
その他、代表例として条例で定められるものに、既存集落内の自己用住宅(長く住んでいる人の建替えなど)、公共事業による収用代替建築物(道路整備等で土地を失った人の代替施設)、災害危険区域からの移転建築物(土砂災害警戒区域等から避難移転する住宅)、自治会施設(集会所・防災倉庫など)、さらには各自治体固有のものとして企業誘致のための工場や流通業務施設を特定区域に限り認める例もあります。
許可事例
分家住宅は多くの農村部で適用されています。例えば佐倉市では、長年調整区域に住む農家から婚姻等で分家する親族が本家近くに住宅を建てる場合に許可を出しています。
また、都市計画道路予定地内の家屋移転で代替住宅を調整区域内に建築した例(公共事業代替)、土砂災害特別警戒区域から安全な場所へ家を建て替えた例(災害移転)なども条例12号で許可されています。自治会集会所についても地域の要望で建設された事例があります。各地で「地域ニーズに応じた例外」が運用されています。
許可条件
条例で個別に定めるため、その内容・条件は自治体ごとに異なります。共通しているのは「市街化を促進するおそれがない(スプロールにならない)」ことと「市街化区域内で代替困難」であること。例えば分家住宅の場合、多くの条例で以下のような属人要件があります。
- 申請者は調整区域に長年居住する本家世帯の親族であること(〇親等以内など制限あり)。
- 本家から世帯分離する正当な理由があること(婚姻等)。
- 申請者が自分名義の家を持っていないこと。
- 本家と一定年以上同居していた実績があること。
- 本家も申請者も市街化区域内に代替となる宅地を持っていないこと。
- 過去に同様の許可を受けていないこと。
- 建設場所は本家所有の土地かその近隣であること。
- 良好な農地や自然保全地区を含まないこと、敷地500㎡以下など面積制限等。非常に厳格です。
こうした属人的条件から、分家住宅で建てられた家は本人限りの使用が原則で、転売や他用途転用には制限がかかります(再建築不可の場合も)。第12号全般でも、用途・区域ごとに細かな条件設定がされており、許可の際はそれらをすべて満たす必要があります。
都市計画法第34条第13号:線引き時の既得権による自己用建築
都市計画法第34条第13号:線引き時の既得権による自己用建築について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
調整区域の線引きを新たに決定または変更して市街化調整区域が拡大された際に、その決定日以前から当該土地について所有権その他の権利を有していた者で、決定日から起算して6か月以内に所定事項を知事に届け出たものが、自己の居住または業務の用に供する建築物等を建てる目的で行う開発行為(かつ政令で定める期間内に行うもの)が対象です
新規線引きによる不利益を緩和する経過措置的規定です。
主な用途例
自己居住用の住宅や自己事業用の建物が典型です。たとえば、線引き変更前に購入済みの宅地について家を建てようとしていた人が、区域区分変更で突然調整区域になってしまった場合でも、この条項に該当すれば自宅を建築できます。
また、自社工場用地として取得済みだった土地が調整区域に入ってしまった場合でも、業務用施設の建設が許可され得ます。
許可事例
昭和40~50年代に線引きされた地域では、この第13号による許可が多く出されました。例えば△△市では197X年の線引き当時に権利者届出があった数十件について、以後5年以内に順次住宅建築が行われています。
また、平成に入ってからの区域区分変更(調整区域拡大)時にも、既に開発計画を持っていた業者が届出を行い、小規模工場を建設したケースがあります。これらはいずれも線引き前からの権利を行使したものです。
許可条件
最大のポイントは期限内の届出です。区域区分決定(線引き)または変更の日から6か月以内に「自分はこの土地に家(または工場)を建てる予定だった」という内容を知事に届け出なければなりません。届出をしていなければ第13号適用は受けられません。
そして、届出者は決定時点で土地の権利を有していた者に限られます(決定後に土地を取得した場合は適用外)。許可は政令で定める期間内に行う開発行為に限るとされ、現在は届出日から5年以内程度とされています(具体的期間は政令規定)。用途も自己利用に限定され、分譲住宅を建てる等は認められません。
この許可で建てた建物を他用途に転用することも制限されます。要するに、線引きで割を食った人への一度きりの救済措置であり、期限と本人利用が厳格に管理されます。
都市計画法第34条第14号:開発審査会議決を経るその他の開発行為
都市計画法第34条第14号:開発審査会議決を経るその他の開発行為について、条文概要、主な用途例、許可事例、許可条件についてまとめています。
条文概要
上記第1号~13号に該当しない開発行為であっても、都道府県知事が開発審査会(行政の附属機関)の議を経て、「当該開発行為が周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当」と認める場合には開発許可をできる、とする包括的な規定です。俗に「開発審査会基準」と呼ばれ、個別審査による特例許可を指します。
主な用途例
第14号で許可される例は多岐にわたります。典型的なものを挙げると以下の通りです。
- 宗教施設:寺院・神社の移転新築、納骨堂の建設。
- 研究施設:調整区域内の自然環境や資源を研究対象とする大学・企業の研究所。
- 社員寮・社宅:郊外工場の従業員用住宅や企業の研修寮。
- 公営住宅:自治体が過疎地対策等で建設する公営住宅。
- 既存建築物の建替え・増築:用途変更も含め、既存不適格建物の改良。
- 都市内危険区域からの移転:市街化区域内の災害危険地区にある建物を安全な調整区域へ移す。
- レクリエーション施設:大規模なキャンプ場やスポーツ施設の付帯建築物。
- 小規模工場:条例11号区域外でも特定の既存集落内に限り工場を認めた例。
- 物流拠点:一定の指定区域内で大規模物流倉庫を建設(地域経済上必要な場合)。
- 社会福祉施設:老人ホームや障害者施設など大規模な福祉施設。
- 建物用途転換:長年適正利用された建物を賃貸住宅等に転用(定住促進目的)。
- 地域産業振興施設:地場企業の工房や観光交流施設など。
- 最低限の管理施設:広大な土地の維持管理に必要な管理棟など。
許可事例
全国各地で様々な事例があります。例えば、都市近郊の調整区域に大学の実験農場と研究棟を建設したケースでは第14号許可が活用されました。
また、老朽化した寺院を郊外の広い土地に移転新築した例、製造業の物流ニーズに応えるため調整区域沿いの幹線道路沿いに大規模物流センターを建設した例(プロロジスパーク○○等)もあります。
さらに、過疎集落の振興策として自治体が定住促進住宅(賃貸)を整備したり、既存の空き公共施設を転用して福祉施設にした事例など、多岐にわたります。第14号はいわば「ケースバイケース」の許可であり、開発審査会が妥当と認めればかなり柔軟な対応が可能です。
許可条件
開発審査会の議決を経ることが法定要件です。申請案件ごとに審査会(学識者等で構成)が開かれ、周辺市街化への影響、都市内で代替できない理由、公益性、規模の適正、環境配慮など多角的に検討されます。その上で許可すべきと議決されれば知事が許可します。従って審査会基準と呼ばれる内部基準が各都道府県に存在し、「どういう案件なら審査会を通すか」をガイドライン化しています。
例えば、物流施設なら「都市計画マスタープランで物流拠点と位置付けられた地域であること」等、事前相談の段階で絞り込まれます。
許可に際しては個別条件が付されるのも通例です。たとえば寺院移転では旧寺院跡地を宅地開発しないことを条件にしたり、物流倉庫では周辺道路の整備負担を求めたりと、開発による副次的な市街化影響を抑える措置が講じられます。総じて第14号は最後の砦的な位置づけで、公共性・公益性の高いものか、地域にとって必要不可欠なもののみが慎重に許可される傾向があります。
市街化調整区域における雑種地の相続税評価に係るしんしゃく割合の目安
相続税評価で雑種地の「しんしゃく割合」は、建物がどの程度建てられる見込みか(=34条各号の当たり方)によって大きく変わります。
下の一覧では、地区計画や既存集落の区域指定で「宅地並み」に建てられるケースを原則0%、用途を絞れば建築可能なケースを30%、いずれの号にも当たらず建築が見込めないケースを50%の目安として、代表的なシーンを並べました。
あくまで実務上の基準感であり、最終的な評価は個別の条例運用や接道・インフラ状況、周辺の市街化の度合い、地形・地積、取引実勢等によって前後します。
評価にあたっては、該当し得る34条の号を早期に見極めつつ、自治体の最新運用や技術基準、農地転用の要否なども併せて確認してください。
| 34条の立地基準の当たり方(代表例) | 建築の実務的見込 | しんしゃく割合の目安 | 典型シーン |
|---|---|---|---|
| 第10号(地区計画・集落地区計画)第11号(既存集落の区域指定)で自己用住宅等が計画どおり建てられる | “宅地並み”に建築可 | 0%(減額なし) | 指定区域内の自己住宅や小規模店舗の建築が通常に行われる集落内の画地。 |
| 第1号(日常利便施設=いわゆる一号店舗)第9号(沿道休憩・給油等)など、用途を絞れば建築が見込める第12号:(分家住宅等) | 建築可だが用途・構造に制限 | 30% | 幹線道路沿いで物販は不可だが休憩所・給油所は可、既存集落で日用品店なら可、農家分家だけ可…など制約つきの立地。 |
| 上記各号に該当せず、開発許可・建築が見込めない | 建築不可 | 50% | 既存集落から離れ、34条の当たりが立たない資材置場・駐車場的利用の地。 |
代表的な当てはめ例(ケーススタディ)
市街化調整区域の土地評価では、同じ「雑種地」であっても、どの号に当てはまるか(=建築の実現可能性)によって評価のしんしゃく割合は大きく変わります。
以下の表では、第10号・第11号などの住宅が普通に建つ区域から、第9号・第1号といった用途限定で建築が許される区域、そして34条の当たりが立たない実質的な非建築地まで、代表的なケースを整理しました。
最終的な評価は、区域の指定状況、接道やインフラの整備度、周辺の市街化の進行度、利用実態などを総合的に勘案して決定されます。
したがって、下記の目安を基準としつつも、「建てられる」ではなく「どの程度の用途で建てられるか」を丁寧に見極めることが重要です。
- 集落地区計画内(第10号)で自己用住宅が普通に建つ画地
→ 市街化の影響も強く、実質“宅地並み”。**しんしゃく0%**が原則。 - 既存集落の区域指定(第11号)内。自己住宅は建つが、工場や大型店は不可
→ 住宅等は建つ=宅地比準が基本。多くは**0%だが、周辺の市街化影響が弱ければ0〜30%**で個別判断。
- 幹線沿いで“休憩所や給油所なら可”(第9号)
→ 建築は可能だが用途が絞られる。**30%目安。実勢が宅地並みに近い商業的ホットスポットなら0〜30%**で調整。 - 集落外の資材置場(雑種地)。34条の当たりが立たない
→ 建築不可の代表格。**50%**目安。 - 一号店舗(第1号):既存集落内で日用品店なら可
→ 用途限定の建築可。30%が目安。周辺が半ば市街化的なら0〜30%。
おわりに
以上、都市計画法第34条各号に基づく市街化調整区域の開発許可の立地基準について、その概要、具体例、そして自治体ごとの運用状況を整理しました。
都市計画法第34条は、市街化の抑制という大原則のもとに設けられた限定的な例外規定であり、その適用には厳格な要件が求められます。とりわけ、要件や解釈の運用は自治体ごとに条例・基準が異なるため、開発を検討する段階で早期に自治体と事前協議を行うことが極めて重要です。
また、人口減少や防災意識の高まりを背景に、第8号の2(災害危険区域からの移転許可)など、制度自体も時代に合わせて改正・追加されています。
こうした制度変化を踏まえ、調整区域における土地活用は「現在の基準」で再確認することが欠かせません。
さらに、相続や売却の場面で問題となる雑種地の相続税評価額についても、建築の可否に応じたしんしゃく割合が判断のポイントとなります。
一般的には、第10号・第11号のように既存集落や地区計画に基づく建築が可能な土地は0%寄り、第1号・第9号・第12号など用途が限定される土地は30%寄り、そして建築が困難な土地は50%程度が基準とされます。
ただし、最終的な評価は地域の実勢や個別事情を踏まえて総合的に判断することが重要です。