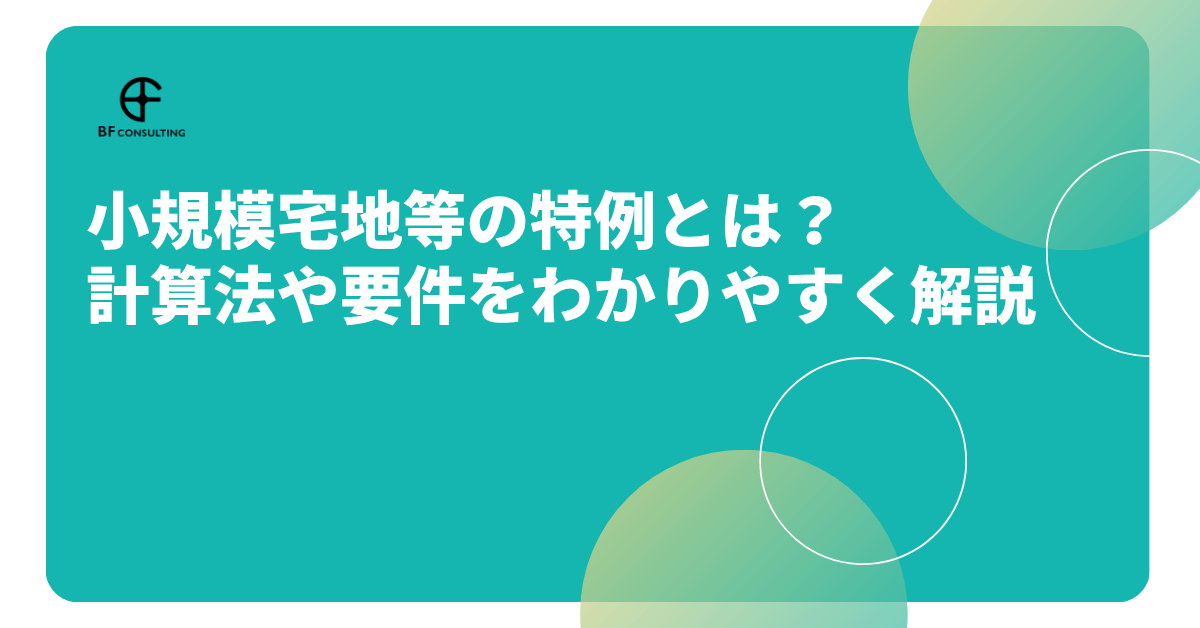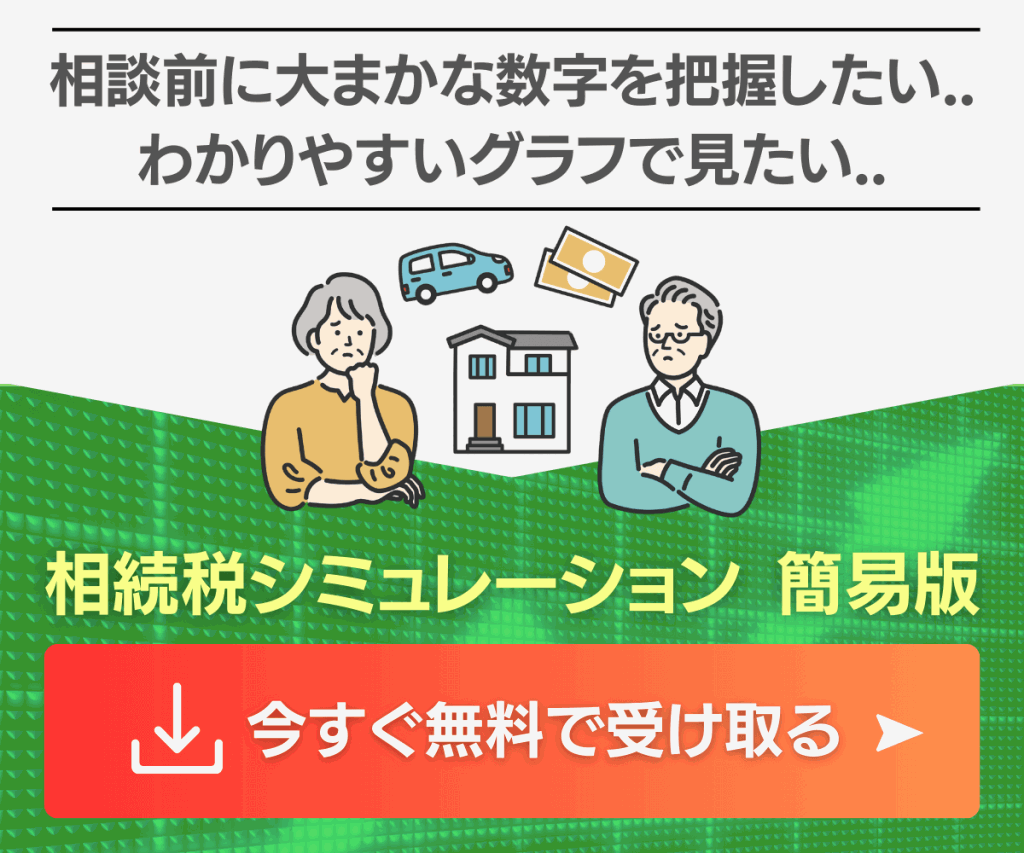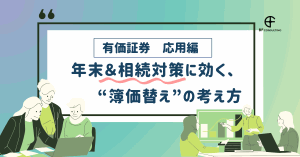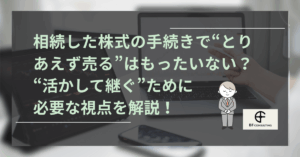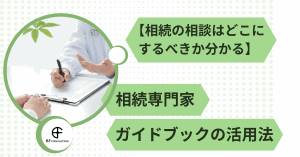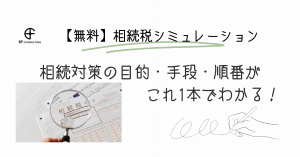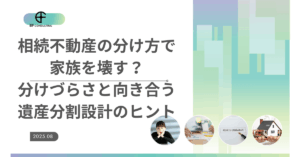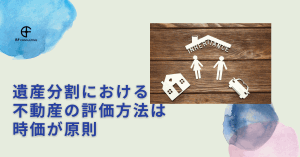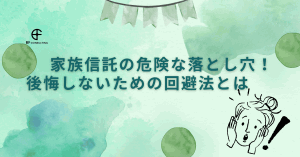「小規模宅地等の特例」の計算法や要件をわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例は、相続税の減額効果が大きいため、活用したい特例です。
特例の適用により、相続税の支払いが免除されるケースも珍しくありません。
この記事では、小規模宅地等の特例の適用要件をわかりやすく整理しました。
相続税の支払いが気になる人は、ぜひとも参考にしてください。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、不動産の相続税評価額を減額できる制度です。
相続税が多額になると、税金の支払いのために、生活の拠点となる自宅や、代々続く家業の店舗を手放さざるを得なくなります。
しかし、税金の支払いを理由に生活の拠点や家業を失うのは酷です。
小規模宅地等の特例は、そのような不幸から相続人を守るために作られました。
小規模宅地等の特例が適用されると、不動産の相続評価額が最大で80%下がります。
特例の適用で、相続税の支払いを免れるケースも珍しくありません。
小規模宅地等の特例の対象となる土地は3種類
小規模宅地等の特例は、3種類あります。
土地の種類によって、適用要件や評価額の減額割合が異なります。
| 土地の種類 | 具体例 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地 | 自宅 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 八百屋 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | アパート | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地
特定居住用宅地に該当する宅地は、次のとおりです。
- 被相続人の居住に供されていた
- 被相続人と同一生計の親族の居住に供されていた
両親が住んでいた実家の土地は、特定居住用宅地等の典型例です。
被相続人のみならず、被相続人の親族が住んでいた住居も特例の対象になります。
「同一生計」とは、同じ財布で生活をともにしている状態です
「居住に供されていた」とは、住居のために使われていたという意味です。
なお、小規模宅地等の特例の適用は宅地が対象になります。
建物のない更地は適用対象から外されます。相続人の生活の本拠や代々続く家業を守るのが、小規模宅地等の特例の趣旨だからです。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等に該当する宅地は、次のとおりです。
- 被相続人の事業に供されていた
- 被相続人と同一生計の親族の事業に供されていた
両親が事業を営んでいた際の、店舗のある土地が、特定事業用宅地等の典型例です。
被相続人のみならず、被相続人の親族が事業に使っていた土地も、特例の対象になります。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等に該当する宅地は、次のとおりです。
- 被相続人の不動産貸付業に供されていた
- 被相続人と同一生計の親族の不動産貸付業に供されていた
両親が不動産賃貸業を営んでいた場合の、マンションやアパートの土地が、貸付事業用宅地等の典型例です。
被相続人のみならず、被相続人の親族が不動産貸付業に使っていた土地も、特例の対象になります。
特定居住用宅地等の場合
特定居住用宅地等に小規模宅地等の特例が適用される場合の、計算例や適用要件、添付書類について解説します。
特定居住用宅地の計算例
評価額が5,000万円の実家の土地(300㎡)を、一人で相続した場合を考えてみましょう。
相続人は一人であるため、基礎控除は3,600万円(3,000万円 + 600万円 )です。
相続財産(5,000万円) > 基礎控除(3,600万円)となり、通常であれば、相続税の支払いが必要です。
しかし小規模宅地等の特例の申請で、相続財産の評価額を下げられます。
実家の土地は、特定居住用宅地に該当するため、減額割合は80%です。
小規模宅地等の特例が適用される結果、相続税評価額は、1,000万円まで減額されます。
計算式は次のとおりです。
5,000万 ‐(5,000万×0.8)= 1,000万円
実家の土地・建物以外に相続財産がない場合、相続税評価額は基礎控除の範囲内におさまる可能性が高く、相続税の支払いが不要になります。
小規模宅地等の特例が存在しなければ、基礎控除の範囲内におさまらず、相続税を支払わなければいけません。
相続財産に現金や株式がない場合、実家を売却して税金を支払うことになるでしょう。
特定居住用宅地等の適用要件
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を申請するには、次の要件を満たす必要があります。
- 相続した土地が特定居住用宅地等に該当する
- 申請者の要件を満たす
- 必要書類を揃えて申請する
cf 要件を満たした場合に減額される土地評価額
| 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|
| 330㎡ | 80% |
相続した土地が特定居住用宅地等に該当する
適用対象となる土地は次のとおりです。
- 被相続人の居住に供されていた
- 被相続人と同一生計の親族の居住に供されていた
申請者の要件を満たす
申請できる人は次のとおりです。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同居していた親族
- 被相続人と生計が同一だった親族
- 家なき子特例の要件を満たす親族
申請者によって、適用要件は異なります。
| 申請者の種類 | 適用要件 |
|---|---|
| 配偶者 | 土地の所有 |
| 同居していた親族 | 相続税申告期限までに土地を所有し居住を継続する |
| 生計が同一だった親族 | |
| 家なき子特例の要件に該当する親族 | 要件の詳細は、国税庁のホームページを参照 |
被相続人の配偶者は、対象となる土地を所有するのみで、申請者の要件を満たします。相続により土地を取得すればよく、実際に住む必要はありません。
配偶者が申請するケースでは、小規模宅地等の特例が適用されやすい仕組みになっています。
一方で、配偶者以外の親族が申請する場合、適用要件は厳しくなります。
相続税の申告期限内に、対象となる土地を所有し、住居に住まなければいけません。所有のみならず、実際に住むことが要件になっています。
相続税の申告期限は、通常、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内です。
1月10日に死亡した場合、その年の11月10日が申告期限になります。
家なき子特例
自立して一人暮らしをしている息子や娘など、生計をともにせず、かつ被相続人と同居していなかった親族でも、小規模宅地等の特例の適用をうけられる余地があります。
家なき子特例と呼ばれるケースです。
家なき子特例の要件は複雑で、要件クリアのハードルは高いです。
一人暮らしで、賃貸マンション以外に住む場所がない人は、家なき子特例の適用を満たす可能性が高いといえます。
要件の詳細は国税庁のホームページを参考にしてください。
必要書類を揃えて申請する
小規模宅地等の特例は、申請が適用の要件です。
必要書類を揃えて、税務署に特例の利用を申請しない限り、土地の相続税評価額は減額されません。
特例が適用される結果、相続税が0になるケースであっても、税務署への申請は必要です。
小規模宅地等の特例は、申請してはじめて減額効果が生じます。
特定居住用宅地等に必要な添付書類
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の添付書類は次のとおりです。
- 遺産分割協議書または遺言書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の相続人を明らかにする戸籍謄本
上記は、最低限、必要になる書類です。
状況によっては、追加の添付書類が必要になります。
特定事業用宅地等の場合
特定事業用宅地等に小規模宅地等の特例が適用される場合の、計算例や適用要件、添付書類について解説します。
特定事業用宅地等の計算例
評価額が1億円の特定事業用宅地等(400㎡)を相続する場合
特例適用後の土地の評価額 = 1億円 ‐(1億円万×0.8)= 2,000万円
特定事業用宅地等の適用要件
小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)を申請するには、次の要件を満たす必要があります。
- 取得した土地が特定事業用宅地等に該当する
- 申請者の要件を満たす
- 必要書類を揃えて申請する
cf 要件を満たした場合に減額される土地評価額
| 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|
| 400㎡ | 80% |
特定事業用宅地等に該当する宅地は、次のとおりです。
- 被相続人の事業に供されていた
- 被相続人と同一生計の親族の事業に供されていた
上記に該当する場合でも、相続開始前3年以内に事業用に使われ始めた土地は、原則として特例の対象外です。対象から外されるのは、小規模宅地等の特例を利用した相続税対策を防ぐためと考えられます。
申請者の要件は、次のとおりです
- 被相続人の親族が
- 相続税申告期限までに
- 土地を取得し
- 事業を継続する
必要書類を揃えて、税務署に特例の利用を申請しない限り、土地の相続税評価額は減額されません。
特定事業用宅地等に必要な添付書類
添付書類は、特定居住用宅地等と共通します。
ただし状況によっては、定款の写しや出資額の総額、発行済株式数など、法人に関する書類の提出が必要です。
貸付事業用宅地等の場合
貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例が適用される場合の、計算例や適用要件、添付書類について解説します。
貸付事業用宅地等の計算例
評価額が1億円の貸付事業用宅地等(200㎡)を相続する場合
特例適用後の土地の評価額 = 1億円 ‐(1億円×0.5)= 5,000万円
貸付事業用宅地等の適用要件
小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を申請するには、次の要件を満たす必要があります。
- 取得した土地が貸付事業用宅地等に該当する
- 申請者の要件を満たす
- 必要書類を揃えて申請する
cf 要件を満たした場合に減額される土地評価額
| 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|
| 200㎡ | 50% |
特定事業用宅地等に該当する宅地は、次のとおりです。
- 被相続人の不動産貸付業に供されていた
- 被相続人と同一生計の親族の不動産貸付業に供されていた
上記に該当する場合でも、相続開始前3年以内に不動産貸付業用に使われ始めた土地は、原則として特例の対象外です。対象から外されるのは、小規模宅地等の特例を利用した相続税対策を防ぐためと考えられます。
申請者の要件は、次のとおりです
- 被相続人の親族が
- 相続税申告期限までに
- 土地を取得し
- 動産貸付業を継続する
必要書類を揃えて、税務署に特例の利用を申請しない限り、土地の相続税評価額は減額されません。
貸付事業用宅地等に必要な添付資料
添付書類は、特定居住用宅地等と共通します。
ただし状況によっては、追加書類の提出が必要です。
特別な事例を紹介
小規模宅地等の特例が適用される、特殊なケースを紹介します。
耕作された農地も適用される事例
耕作された農地は、原則として、小規模宅地等の特例の適用対象外です。
小規模宅地等の特例対象となる土地は、建物の敷地だからです。
もっとも、建物と同視できる構築物のある農地に限っては、特定事業用宅地等に該当し、特例が適用される可能性があります。
建物と同視できる構築物の具体例は、次のとおりです。
- 農業用耕運機
- トラクター
- 農機具置場
- 農作業場
マンションも適用される事例
マンションにも小規模宅地等の特例が適用される余地があります。
しかし、マンションは敷地が他人との共有になっており、権利関係が複雑です。
また被相続人本人が住んでいたのか、賃貸物件として他人に貸し出していたのかによっても、適用される特例の種類が変わります。
通常にくらべて評価額算定の難易度は上がりますが、マンションにも特例が適用されうることは知っておいて損はありません。
都会の高層マンションは相続税の評価額が高額になるため、小規模宅地等の特例を申請するメリットは大きいです。
よくある質問
- 小規模宅地の特例とはどういう意味ですか?
-
条件を満たすことで、不動産の相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。
- 小規模宅地の特例の対象者は?
-
特例が使えるのは3人です。
- 配偶者
- 同居親族(住民票が同じでも実際に同居していないと対象にならない)
- 家なき子
- 小規模宅地の特例は申告不要ですか?
-
申告は必要です。ご自身で計算をして、遺産相続が基礎控除よりも少なくなれば申告不要ではないか?と思われるかもしれませんが、小規模宅地等の特例を適応するには申告する必要があるので注意をしましょう。