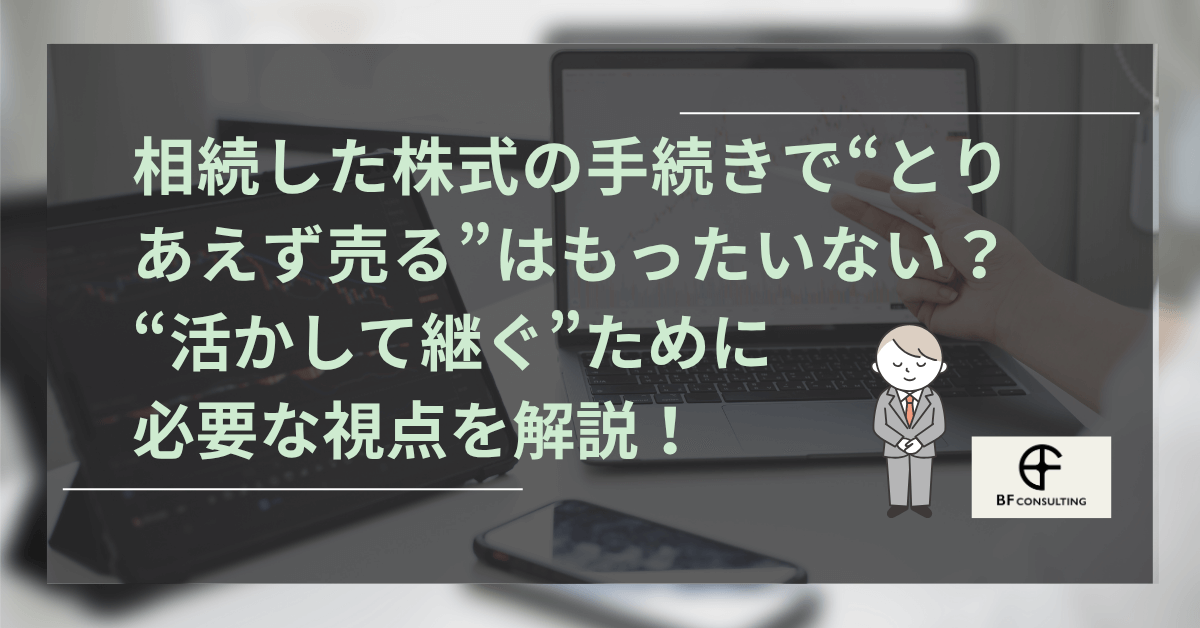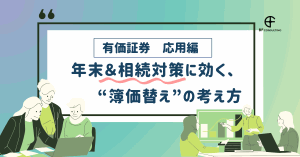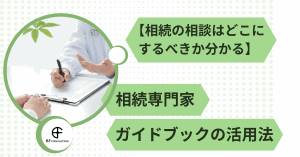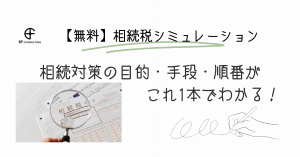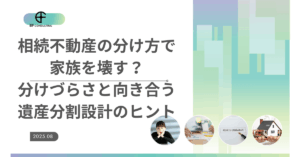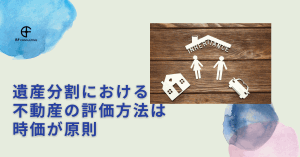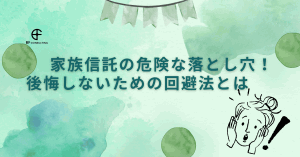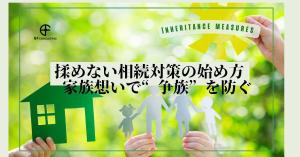証券会社に預けている株式や投資信託、債券など....
NISAの広がりにより有価証券が比較的身近になった世の中とは言え、やはり「株とか有価証券はよくわからない・・・」という方は少なくはありません。
「相続になったら不動産と現金に分けましょう」「有価証券はとりあえず売却してから分けた方が無難ですよ」
こういったアドバイスを、士業の先生方や関係者から聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
確かに、有価証券や株式は価格が日々変動し、遺産分割の公平性を保つには厄介な側面もあります。
また、相続人の中には証券投資に慣れていない方もいらっしゃるため、「面倒だから現金にしてしまいたい」と考えるのも自然です。
ですが、本当にそれでいいのでしょうか?
有価証券は「売却して終わり」ではなく、「引き継いで活かす」こともできる資産です。
場合によっては、売却よりも引き継ぎによって得られる価値の方がずっと大きいこともあるのです。
本コラムでは、相続で取得した株式を“売らずに引き継ぐ”際の手続きや注意点、そして有価証券を上手に活かすためのポイントをわかりやすく解説します。
相続人全員が納得できる形で遺産分割を進めるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
\専門家に相談したい..とお悩みのあなたへ/
最適化計画Labo
「相続対策で悩んでいるけど誰に相談したら良いか分からない...」といった方へ各種専門家に無料で質問できるコミュニティをご紹介!
- 「グループチャット」・・・13名の各種専門家に相続や不動産に関する質問ができます!
- 「メールマガジン」・・・相続対策に役立つ情報を得られる!
13名の専門家に相談できる内容
- 建築
- 測量・開発
- 賃貸管理・空き家
- リフォーム・解体
- 不動産売買
- WEB
- 投資家・Youtuber
- 相続対策
- 保険・IFA
- 終活・相続手続き
- 相続・登記
- 法人・登記
- 税務
これから相続対策を始める方や悩んでいる方に役立つコミュニティなので是非ご登録ください!
有価証券や株式は“そのまま引き継ぐ”こともできる
有価証券を相続した場合、必ずしも売却する必要はありません。
証券会社のルールに従って名義変更(口座移管)を行えば、被相続人の保有していた株式や投資信託は、相続人がそのまま引き継いで保有することが可能です。
たとえば、長年保有している株式や、安定した配当を生んでいる銘柄をすぐに現金化してしまうのは、いわば“育てた果実の木を切り倒して果実だけ取る”ようなものです。
将来の配当収入や値上がり益のチャンスを捨ててしまう可能性もあるのです。
さらに、市場が不安定な時期に売却してしまうと、安値で手放してしまうリスクもあります。
せっかく築かれた金融資産を、急いで現金化してしまうのは、時期によっては損失を生む選択にもなりかねません。
有価証券や株式の遺産分割方法について
有価証券や株式の遺産分割方法は3種類あります。前述では名義変更を行なって、引き継いで保有する方法を紹介しました。その他の方法も確認しておきましょう。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
株式をそのまま相続する(現物分割)
現物分割とは、相続人が保有株式を売却せずに、そのまま相続する方法です。
遺産分割の一つの方式であり、被相続人が保有していた上場株式や非上場株式を、現物のまま引き継ぐことを指します。たとえば、相続人が2人の場合、1人が株式すべてを相続するケースもあれば、複数の銘柄を相続人同士で分け合う方法もあります。
具体的には、被相続人が1,500株を保有していた場合、1人あたり750株ずつに分割して相続することが可能です。また、2種類の株式(異なる銘柄)を保有していた場合には、それぞれの株式を別々の相続人が取得することもできます。
株式を売却して、代金を相続人で分ける(換価分割)
換価分割とは、被相続人が保有していた株式を売却し、その売却代金を相続人同士で分ける方法です。
遺産分割の中でも、株式を現金化してから分配するため、相続人間での管理や評価の手間を減らせる手続き方法として選ばれるケースが多く見られます。
まず、相続人の中から代表者を1名決定し、その代表者名義で一度株式を相続します。その後、証券会社などを通じて株式を売却し、得られた代金を相続人全員で分配します。
配分方法は、法定相続分に従うのが一般的ですが、相続人全員の協議による同意があれば、割合を変更することも可能です。
1人の相続人が株式を相続し、他の相続人に代償金を支払う(代償分割)
代償分割とは、被相続人が保有していた株式などの資産を1人の相続人が相続し、他の相続人に対して代償金を支払う遺産分割の方法です。
株式を複数の相続人で分けることが難しい場合に選ばれるケースが多く、相続財産の公平な分配を実現する手続きとして活用されています。
代償金の金額は法定相続分に基づいて算出するのが一般的ですが、相続人全員の協議による同意があれば、別の割合で設定することも可能です。
具体的には、被相続人が保有していた評価額1,500万円の株式を、2人の子のうち1人がすべて取得する場合、もう一方の相続人に750万円の代償金を支払う形で相続を完了させることができます。
有価証券や株式を売却しないメリットとリスク
次に有価証券や株式を売却しないメリットとリスクについて解説します。
相続で取得した株式や投資信託などの有価証券は、「売却する」か「そのまま保有して引き継ぐ」かという判断が大きな分かれ道になります。
相続人全員の協議のもとで手続きを進める必要がありますが、株価の変動・相続税の支払い・証券会社での名義変更など、考慮すべきポイントは多岐にわたります。
一見すると「売却して現金化した方が手続きが簡単」と思われがちですが、実は売却しないことにも大きなメリットがあります。
反対に、株式をそのまま保有し続けることによるリスクや注意点も無視できません。
メリットとリスクのそれぞれの側面を見ていきましょう。
売却しないメリット
売却しないメリットは下記の3つが挙げられます。
- 将来の値上がり益・配当を引き継げる
→ 長期運用していた銘柄は、時間とともに資産価値が増える可能性があります。 - 不動産との“調整弁”として使える
→ 分けにくい不動産と比べ、有価証券は分割・調整しやすい利点があります。 - 資産運用の“哲学”や“方針”も残せる
→ なぜこの銘柄を選んだのか、どのくらいのリスクをとっていたのか。数字以上の価値がある部分です。
売却しないリスク
一方で、売却しないリスクは下記の3つが挙げられます。
- 相続人の間での理解の差
→ 証券投資に慣れていない方が「不安」「面倒」と感じてしまうことがあります。 - すぐに現金化したい相続人との対立
→ 相続税の支払いや生活資金の都合から「今すぐ現金にしてほしい」と希望される場合もあります。 - 手続きの煩雑さ
→ 証券会社ごとに名義変更の手続きが異なり、郵送対応・印鑑書類なども必要になります。
株式を売るべきか?活かすべきか?判断方法
相続した株式を売却すべきか、保有を続けるべきかを判断するポイントを解説します。
株価は常に変動するため、資産価値が上昇する可能性もあれば、評価額が下がるリスクもあります。
そのため、「すぐにまとまった現金が必要」「資産を減らしたくない」という場合には、売却の手続きを行い、より安定的な資産へ移すのも一つの方法です。
一方で、株式を保有するかどうかの判断は、保有銘柄の種類・業績・配当金の有無などを総合的に考える必要があります。
ここでは代表的な3つのケースに分けて、相続した株式の売却・保有の判断基準を紹介します。
なお、以下は一般的な解説であり、実際の売却判断や相続手続きは、証券会社や税理士などの専門家への相談を推奨します。
ケース1:塩漬け株で配当がない場合
「塩漬け株」とは、株価が取得価格を大幅に下回り、売却すると損失が出るため保有を続けている状態です。
もし配当金がなく、今後の株価上昇の見込みも低い場合は、売却を検討したほうがよいでしょう。
特に相続によって取得した株式の場合、被相続人の取得価額を引き継ぐため、実際には損失が出ているケースもあります。
思い切って売却し、譲渡損として確定申告を行うことで、税金の節税効果(損益通算)を得られることもあります。
株式の管理や手続きの負担を減らすためにも、相続財産全体のバランスを見ながら判断すると良いでしょう。
ケース2:グロース株(成長株)で株価が上昇している場合
「グロース株」とは、売上や利益が継続的に成長している企業の株式を指します。
相続した株式の業績が拡大傾向にあり株価も上昇基調であれば、短期的な売却ではなく長期保有も選択肢です。
ただし、相続時点の取得価額(被相続人の購入価格)よりも利益が出ている場合、売却益には譲渡所得税が課税されます。
この際、「取得費加算の特例」(相続開始から3年10か月以内の売却で、相続税を取得費に加算できる制度)を利用すれば、課税額を軽減できる可能性があります。
売却タイミングを見極める際は、税金の負担や評価額の変動リスクも考慮しながら判断しましょう。
ケース3:高配当株・ディフェンシブ株を保有している場合
「高配当株」とは、配当利回りが高く安定した収益を期待できる銘柄を指します。
目安として、東証上場企業の平均配当利回りが約2%前後のため、3%以上であれば高配当株といえるでしょう。
また、「ディフェンシブ株」とは、景気変動の影響を受けにくい業種(食品、医薬品、鉄道、電力、通信など)の株式のことです。
このような株式は継続的に配当金を受け取れる可能性が高く、長期保有するメリットがあります。
相続後も証券口座でそのまま名義変更手続きを行い、安定収益の源として保有を検討してもよいでしょう。
分け方の工夫と、手続き実務のヒント
相続で株式や投資信託などの有価証券を引き継ぐ手続きでは、
「どの銘柄を誰が相続するか」「どの証券会社で名義変更を行うか」といった点を明確にしておくことが重要です。
相続人全員の協議内容を遺産分割協議書に具体的に記載し、
証券会社や信託銀行での手続きをスムーズに進めることで、後々のトラブルや課税リスクを防ぐことができます。
ここでは、株式相続に関する書類の書き方、証券会社ごとの手続きの違い、口座開設時の注意点、古い株式の取得費調査といった、実務上のポイントを詳しく解説します。
遺産分割協議書のポイント
「銘柄名」「株数」「相続人名」などの情報を正確に記載することが大切です。
有価証券は株価の変動によって評価額が日々変わる資産のため、相続時点の評価額を明確にしておく必要があります。
また、公平性を確保するためには、株式などの評価額を基準にしつつ、現金や不動産とのバランスを考慮して代償分割を検討することも有効です。
相続人全員が納得できるよう、税理士や弁護士などの専門家への相談も検討すると良いでしょう。
証券会社による対応の違い
ネット証券(楽天証券・SBIなど)と、店舗型証券(野村、大和など)では、手続きの丁寧さや必要書類、かかる日数も違います。
複数の証券口座がある場合は、どの証券会社にどの銘柄があるかを生前に整理しておくことが非常に有効です。
相続で有価証券を引き継ぐ際は、原則として「被相続人と同じ証券会社に相続人が口座を開設する」必要があります。
この「口座を作るタイミング」こそ、運用方針や投資哲学を引き継ぐ絶好のチャンスです。
一方で、証券口座を親と一緒に確認してみたら「なんとなく買っていた」「こんな商品持っていたっけ?」というケースもあります。
・・・もしかして「証券会社に勧められるままに購入していた」「元本保証だと思っていたけど実は投資商品だった」なんてこともまれに見かけます。
そういった場合は、ご家族を巻き込んで内容をしっかり精査し、必要であれば見直すことも重要です。
“引き継ぐこと”が目的ではなく、“活かしていくこと”が目的だという視点を忘れずにいたいですね。
特に注意!!古い株式の「買値調査」
古くから保有している株式の中には、取得価格が不明なものもあります。
この場合、将来相続人が売却すると、取得費がわからない=「みなし取得費(売却額の5%)」で計算され、売却益にかかる税金が多額になる恐れがあります。
これは相続後の譲渡所得税額に大きく影響しますので、必ず生前に調査・確認しておくことが重要です!
証券会社に確認することはもちろん、銘柄によっては株主名簿の管理をしている信託銀行へ問い合わせが必要なケースもあります。
早めの対応が、将来のトラブルや余計な課税を防ぐことにつながります。
☑チェックポイント:半年に一回郵送で届く「配当通知書」をチェックしましょう!
“不動産”と“金融資産”の合わせ技で考える
不動産は相続において非常に大きなウエイトを占める一方、“分けにくい資産”でもあります。
対して、有価証券や現金は、分けやすさ・柔軟性という点で、バランス調整の「潤滑油」的な役割を果たします。
たとえば:
- 自宅不動産は長男が相続し、次男には相当する有価証券を相続させる
- 不動産を売却するまでのつなぎ資金として有価証券の売却代金を活用する
- 分割協議が長引いたとき、有価証券の配当や売却益で一時的な納税・生活資金をカバーする
ただし、有価証券を納税資金として活用する場合、時価の変動リスクに注意が必要です。
「評価額を基準にしていたのに、実際に売却したときには想定よりも下落していた…」というケースは珍しくありません。
不動産と金融資産を“セットで戦略的に捉える”ことが、これからの相続対策に求められる視点です。
資産と一緒に、“ノウハウ”も引き継ぐということ
相続対策は「税金を抑える」「揉めないようにする」ことが注目されがちですが、本当に大切なのは、“家族が未来につなげて活かせる形にする”ことです。
有価証券や株式の引き継ぎは、単なる資産の移転ではなく、お金との付き合い方、価値観、そして投資哲学の継承という意味を持ちます。
そのためには:
- 生前から家族と運用について会話をしておくこと
- 保有銘柄の背景や思いを共有しておくこと
- 「ただ売って終わり」にしない選択肢を持つこと
これらが、後悔のない相続、そして“活かす相続”への第一歩になるはずです。
そして、この“活かす相続”を実現するには、感覚や経験だけでなく、正しい知識と判断力が欠かせません。
不動産や金融資産をどう組み合わせ、どう守り、どう引き継ぐか、その答えを学ぶことこそが、将来の安心につながります。
ご家族の未来を守るために、OKB勉強会で正しい知識を身につけましょう。
\専門家に相談したい..とお悩みのあなたへ/
最適化計画Labo
「相続対策で悩んでいるけど誰に相談したら良いか分からない...」といった方へ各種専門家に無料で質問できるコミュニティをご紹介!
- 「グループチャット」・・・13名の各種専門家に相続や不動産に関する質問ができます!
- 「メールマガジン」・・・相続対策に役立つ情報を得られる!
13名の専門家に相談できる内容
- 建築
- 測量・開発
- 賃貸管理・空き家
- リフォーム・解体
- 不動産売買
- WEB
- 投資家・Youtuber
- 相続対策
- 保険・IFA
- 終活・相続手続き
- 相続・登記
- 法人・登記
- 税務
これから相続対策を始める方や悩んでいる方に役立つコミュニティなので是非ご登録ください!