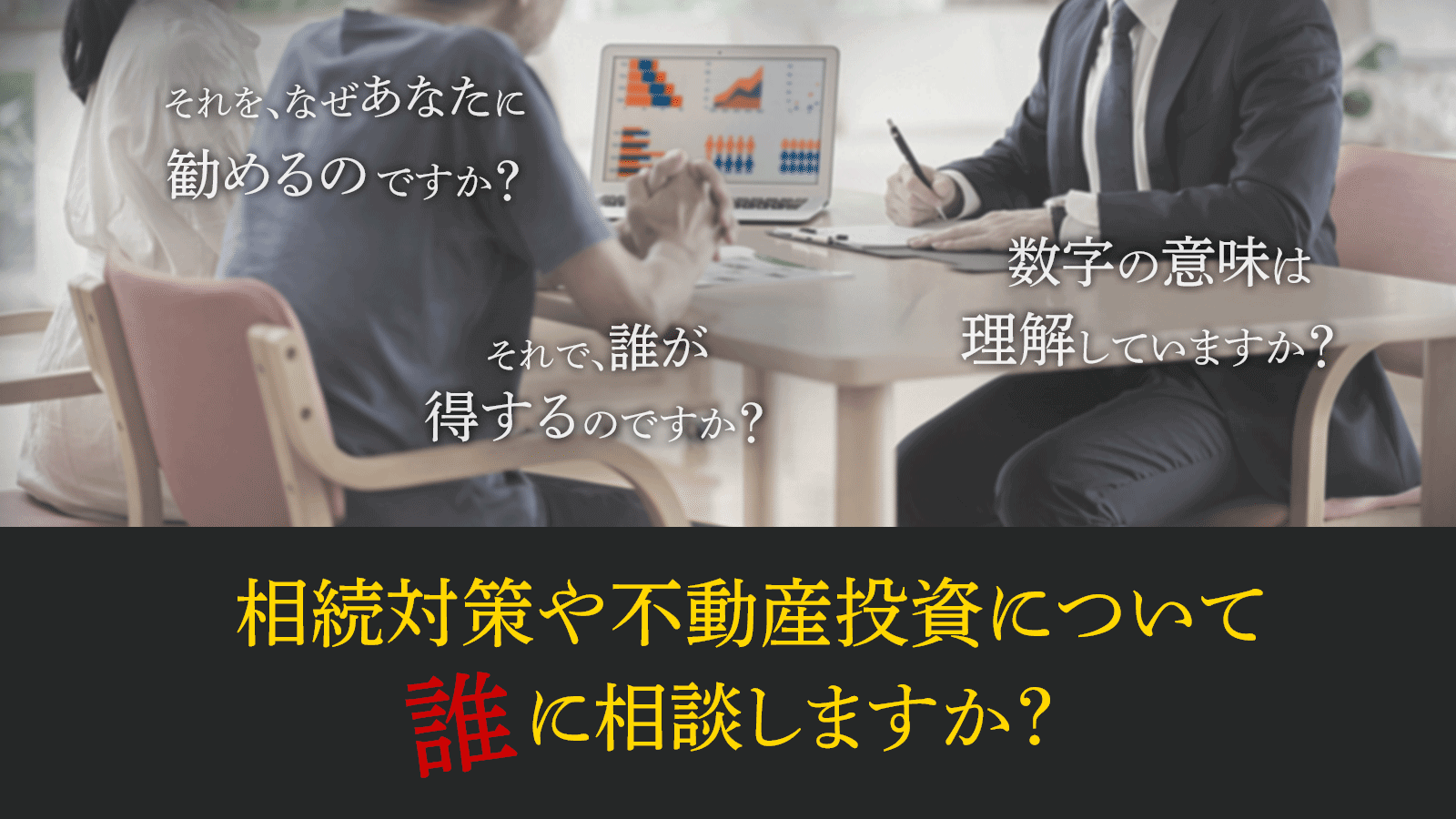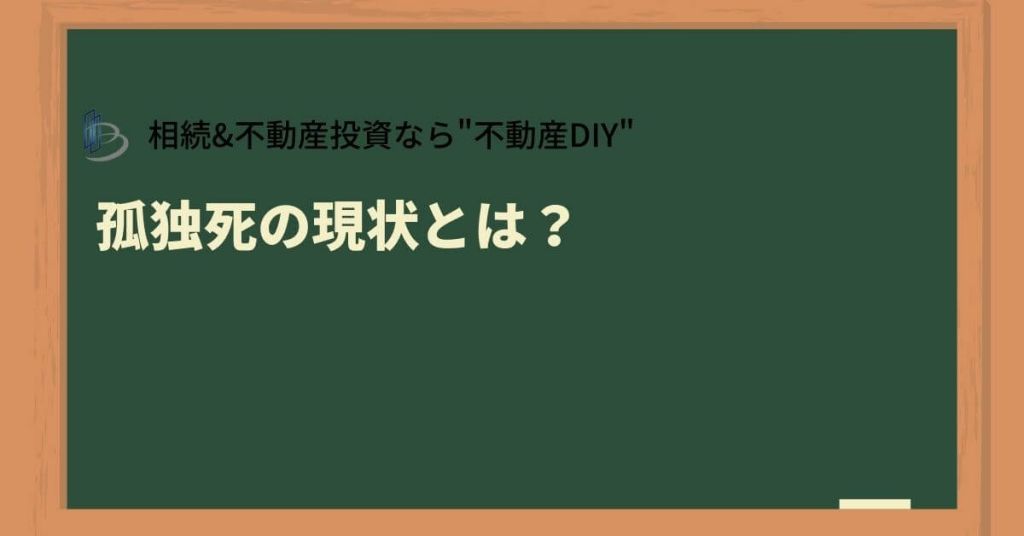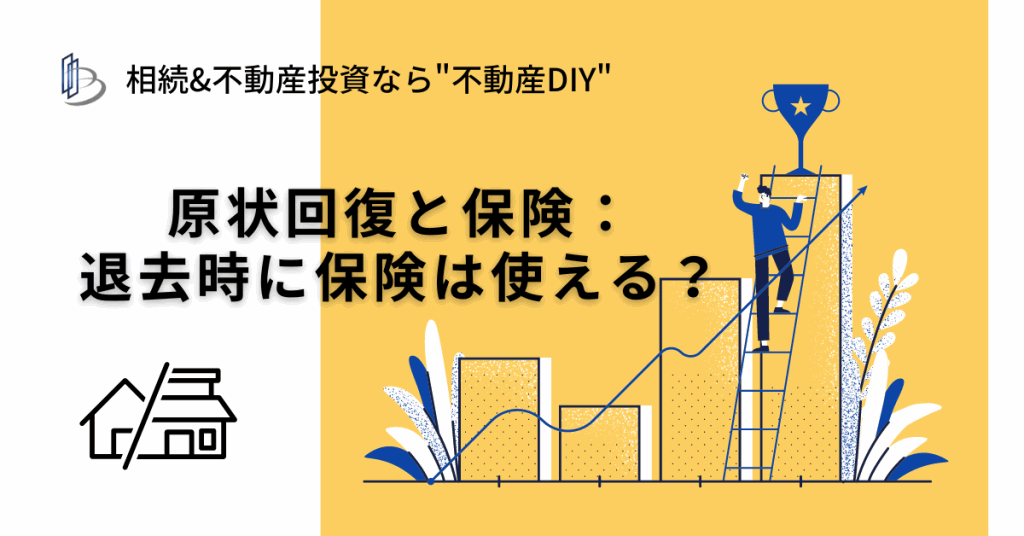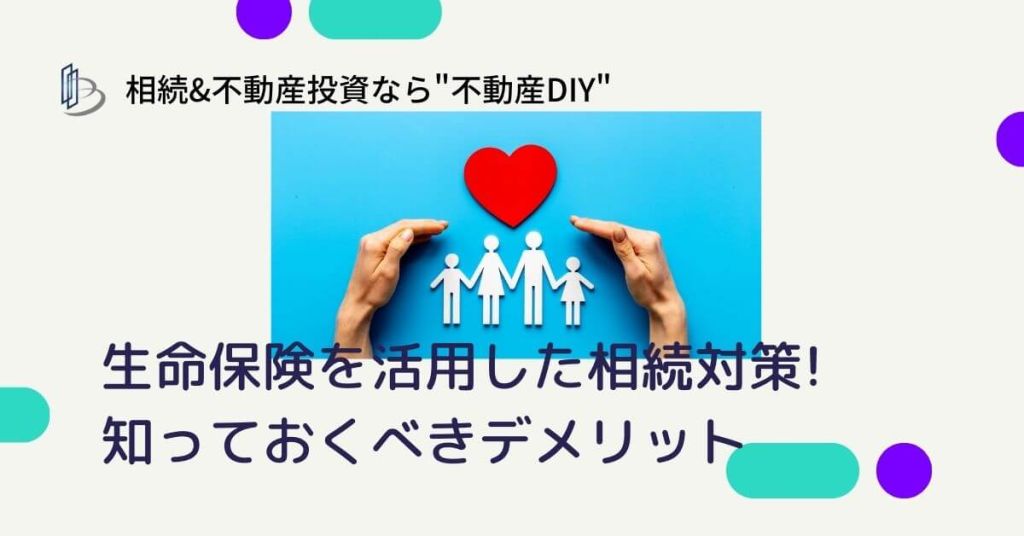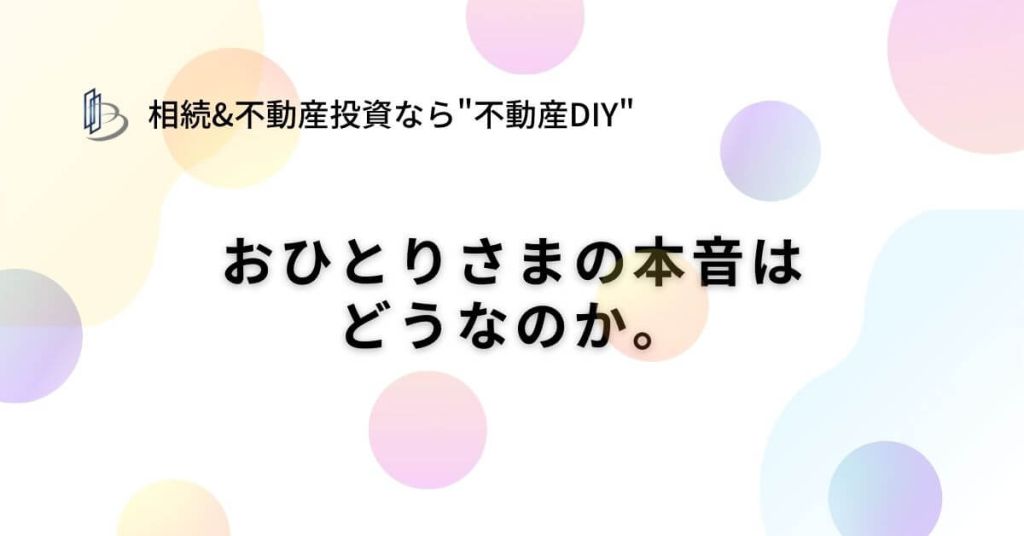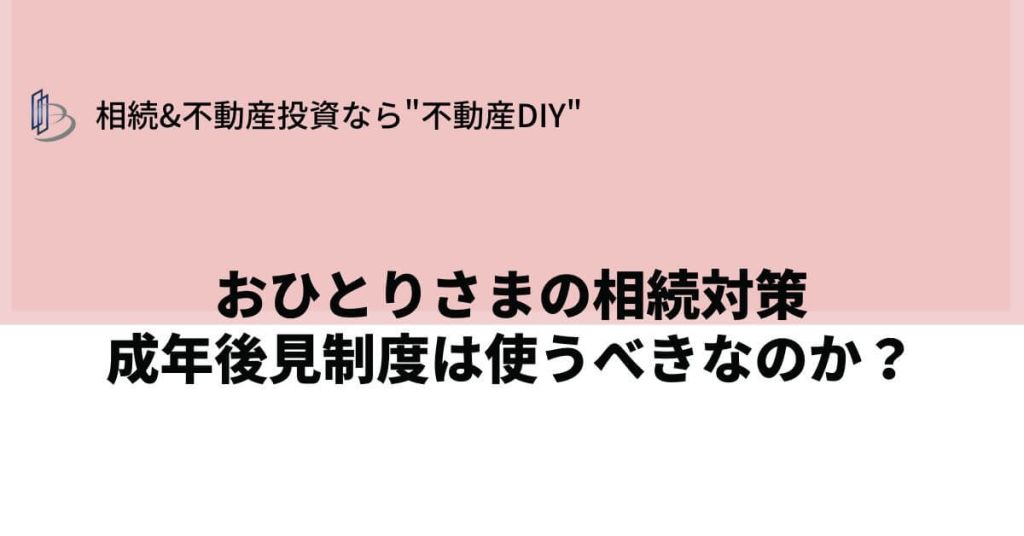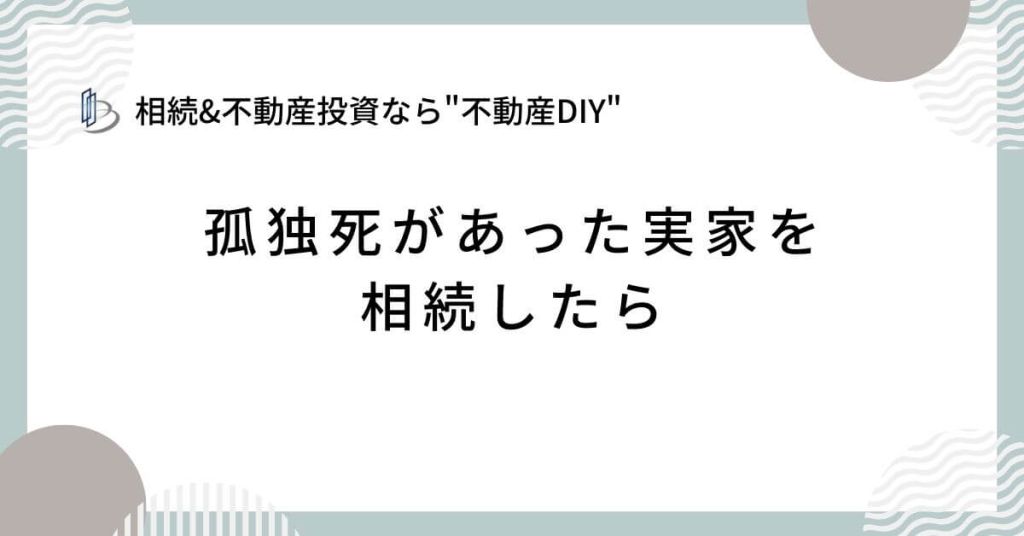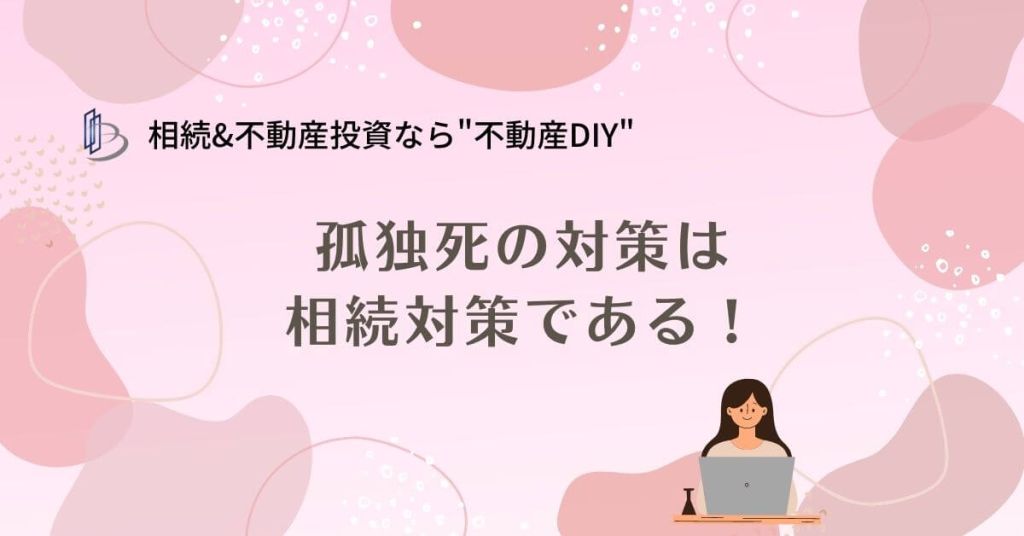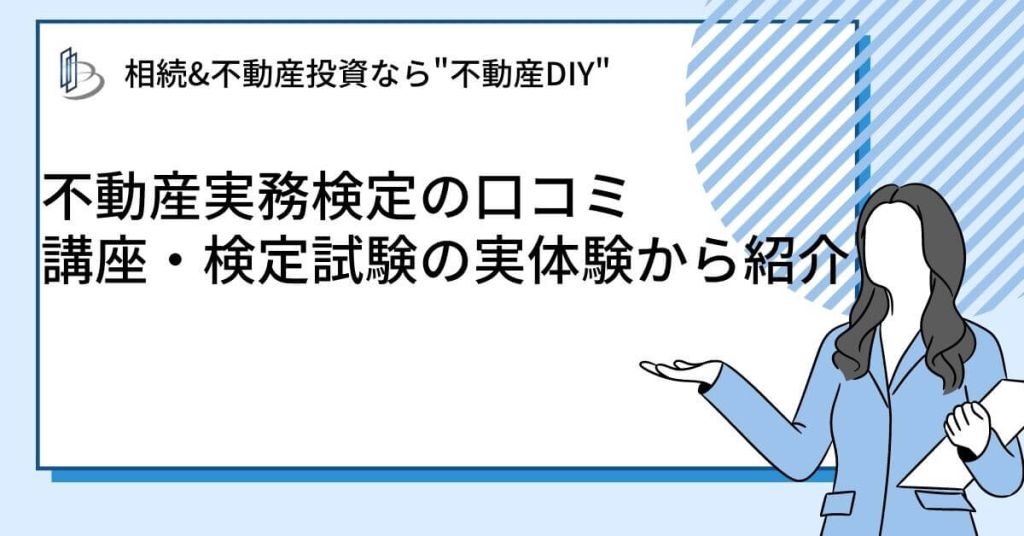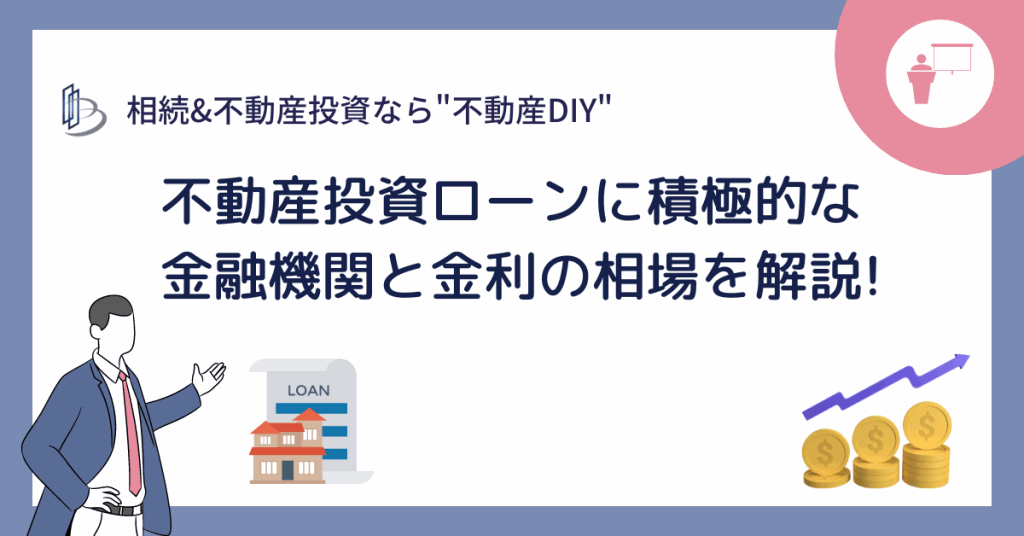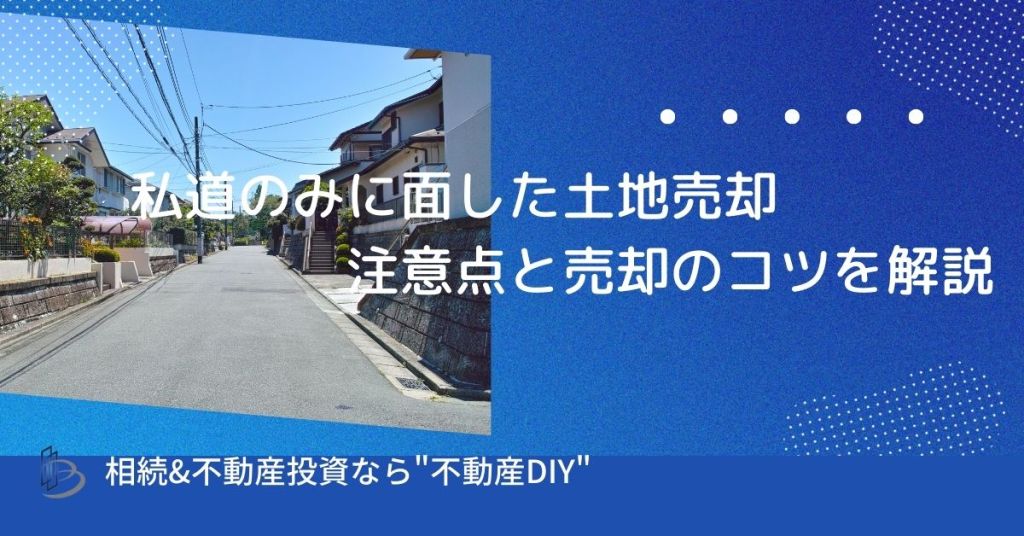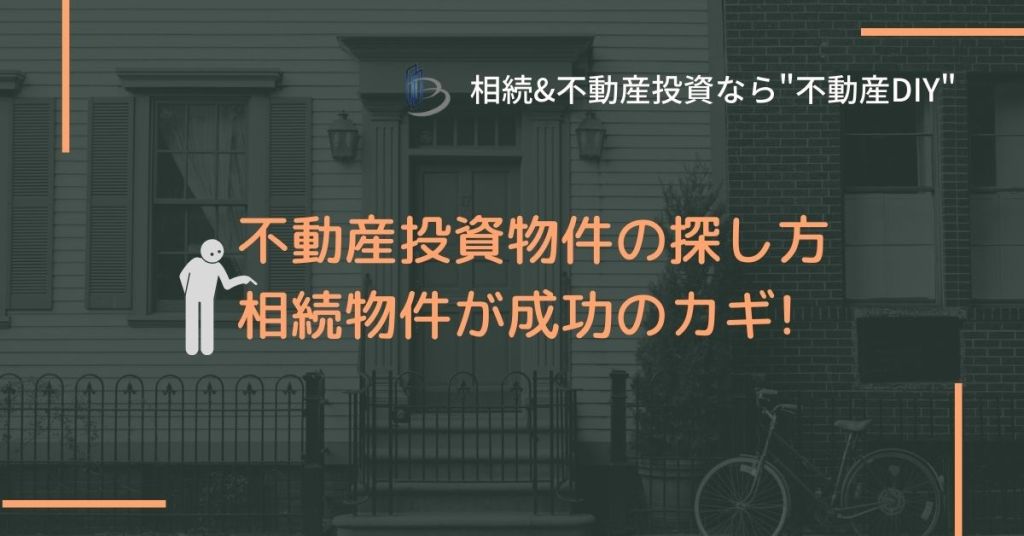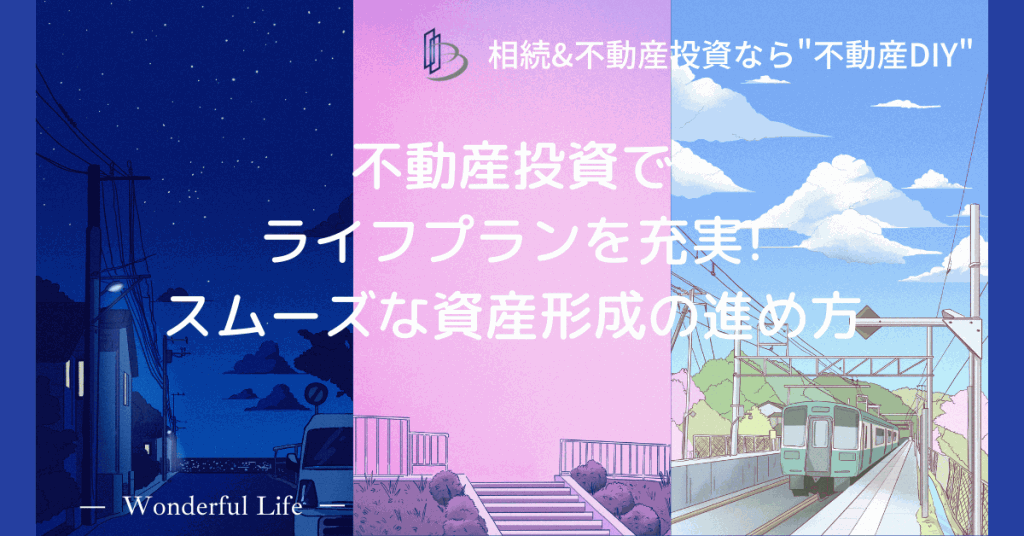お客様の声
GBF0073516:09 14 Jan 23
事業でやる人は別にして、多くの一般人の不動産取引は「必要に迫られて」でしょう。その際いちばん頼りになるのは専門家。特に豊富な経験に裏打ちされたアドバイスや、親身な行動力での現地調査などには既に得がたいものを感じています。最後の★1つ分は、案件が最終的に終結した時にとっておきましょう(^_^) 高田由佳05:54 10 Jan 23
いつもお世話になっています。不動産鑑定士 高田です。岡部社長は相続について広い知識をお持ちで、鑑定評価書の活用場面もよくご存じなので、大変助かっています。お仕事に全力投球の信頼できる方です。 本田啓夫05:39 09 Jan 23
不動産の事以外にも相続の事等も相談に乗ってもらえました。正しい知識を知る事で、私自身も納得してご依頼する事ができました。ありがとうございました。 東優10:20 04 Jan 23
常にお客様目線でご対応いただける信頼感抜群の不動産コンサルタントさんです! 芙二12:01 03 Jan 23
お仕事に関係ない事もお聞きしたり相談させて頂きましたが、必ずお答えくださるのと、返信の速さはすごいです。ご担当いただいたことで、安心してお任せできました。 吉田晃06:34 31 Dec 22
親の相続で相談をしました。相続と不動産投資が密接な関係があることやノウハウなど目からウロコの内容ばかりでした。やっぱり全体を知っている方に頼むのが大切ですね…引き続きよろしくお願いします。 加勢清晴00:43 31 Dec 22
迅速・丁寧 完璧 いつもありがとうございます。信頼してます。 飯沢拓也11:03 27 Dec 22
一つの相談に対して多角的な視点から色々とアドバイスいただきました。とても参考になりました。ありがとうございました。 藤原23:24 22 Dec 22
不動産投資を行う上で重要なポイントを教えて頂きました。税理士の先生とは違う視点からのアドバイスには大変満足しています。